|
「…ス、リーマス。おらんのかのう?」 その声に、ルーピンは無理やり意識を取り戻した。 暖炉のほうから声が聞こえる。ダンブルドアの声だった。 重い体を起き上がらせ、の眠るベッドから下り、ルーピンは声のするほうへ足を運んだ。 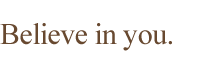 第39話 約束 「ん、…リーマス?」 ドアの音に気付いて、はぼんやりと目を開けた。 さっきまで隣にいたと思っていたルーピンが、今は部屋に入ってきたものだから、 は眠そうな顔をしながら眉を寄せた。 「まだ時間はあるから、休んでいて大丈夫だよ。」 彼女が目を覚ましたのに気付くと、ルーピンは微笑んだ。 ベッドに腰掛けると、彼は付け加えるように言った。 「そうだ、捕まっていたシリウスが逃げた。それも、ハリーたちが救ったんだ。」 「本当に?」 はもう一度瞼を上げて、少し気まずそうに笑った。 だから安心して、と彼女の手を握りながら、ルーピンは優しい声音で囁いた。 も頷いて、またすぐに寝息を立て始めた。 彼女の手首には、何かで縛られた跡が赤く残っていて、指先や手首についた切り傷が痛々しかった。 何より、ルーピン自身がつけてしまっただろう腕の傷には包帯が巻いてある。 彼女はそれらの傷については、一切何も言わなかった。 『このまま私が消えてしまったら、君はどう思うだろう。』 ルーピンは切なそうに彼女の寝顔を見つめ、目を細めた。 「リーマス、門のところに馬車が来ておる。」 「ありがとうございます、校長。」 今朝一番に辞職したルーピンの部屋は、既に荷造りが済み、がらんとしていた。 夏の暑い日差しが、窓から差し込んでいた。 ルーピンは荷物を抱えると、まだ寂しそうな顔をして見送るハリーに微笑みかけた。 「それじゃあ―さようなら、ハリー。 君の先生になれて嬉しかったよ。またいつかきっと会える。」 ルーピンはハリーから、ダンブルドアに視線を移した。 「校長、門までお見送りいただかなくて結構です。一人で大丈夫ですから。」 「そうか。もう皆に挨拶は済んだのかね?」 そうダンブルドアが聞くと、一瞬、ハリーには、ルーピンの視線が自室のドアへ移った気がした。 ええ、と彼が答えると、ダンブルドアは頷き、重々しげに言った。 「それでは、さらばじゃ。リーマス。」 2人はハリーの目の前で握手をした。ルーピンは去り際にハリーのほうを見て、微笑んだ。 そしてその部屋をあとにした。 ふさぎこみ、下を向いたままのハリーの耳に、ドアの閉まる音と、ため息が聞こえた。 「まったく、困ったものじゃ。世話が焼けるといったらないのう。」 「え?」 ハリーが見上げると、ダンブルドアが少し呆れた顔をして彼に笑いかけていた。 「ルーピン先生は、何やら忘れ物をしたようじゃ。」 ダンブルドアは、先程ルーピンが気にしていた部屋のドアを開けた。 ハリーも彼の後に続いて、その部屋へ向かった。 「先生?」 ぐっすりとベッドの上で、が気持ち良さそうに眠っていた。何も知らず、幸せそうな表情で。 「辞職?!」 寝覚めに聞いた一言に、は驚いて目を丸くした。咄嗟に理解できないのは無理もない。 だって、ルーピンは彼女に何一つ言わず出て行ったのだから。 「もう、彼は行ってしまったんですか?」 「そうじゃ。だがもしかしたら、まだ間に合うかもしれん。門のところに馬車が…」 はダンブルドアの言葉を最後まで聞かずに立ち上がった。 慌てて座っていたベッドから下り、部屋の窓を勢いよく開けた。 気持ちのよい風が、一気に部屋に流れ込み、彼女の髪を揺らした。 「わぁっ?!」 ハリーが驚いて叫ぶのと同時に、彼女は窓から飛び降りた。 咄嗟にハリーは窓へと駆け寄った。ダンブルドアは相変わらずのんびりとしたまま、それを見送っていた。 「校長先生、先生が!!」 「大丈夫じゃ。それ、見てご覧。」 落下しながらも、瞬時に箒を呼び寄せたは、城門を目掛けて箒ですごいスピードで飛んで行った。 ハリーも驚くほど、その飛行は早くて、そして美しかった。 「先生は、学生の頃、ハッフルパフ寮のシーカーだったんじゃよ。」 「ええっ」 懐かしむように微笑むダンブルドアを、呆気にとられた表情で振り向いたハリー。 そして、ふと、サイドテーブルの上に置かれたそれに気付いた。 「先生、これ!」 「おや、…もしかすると、本当にわしは余計なことをしてしまったかもしれんのう。」 ダンブルドアはおどけた口調でそう言って、笑った。 ルーピンは門にさしかかり、馬車を見つけると、荷物を座席に乗せ始めた。 とても残念だった。 教師として過ごしたこの一年は、いろいろあったけれど、とても充実した素晴らしい日々だった。 友であるシリウスが戻ってきた。ジェームズの息子、ハリーも立派に成長した。 そして何より、彼女と出会えた。 彼がのことを考えていると、突然、遠くから声が聞こえた。 「待って!!」 彼女の声と分かるなり、ルーピンは驚いて振り向いた。 それと同時に、すぐ目の前まで飛んできたは、箒から飛び降りた。 「わわっ」 ルーピンは彼女を受け止めようとしたが、勢いがあったので、を抱きとめながらその場で転倒した。 彼女の持っていた箒が、地面に転がった。 「、痛いっ」 石畳に打ち付けた頭をさすりながら、彼が上半身だけ起き上がると、 上に跨って乗っかっているも顔を上げた。 刹那― バチンッ の平手が、ルーピンの頬を打った。 驚いてルーピンは彼女を見た。は頬を上気させて、本気で怒っているようだった。 「?」 初めは何がなんだか分からなかったルーピンだが、すぐに思い当たった。 そして慌てて彼女をなだめようとした。だが、 「馬鹿!!!」 ルーピンの襟元を掴んで、は怒りで震えながら叫んだ。 「待ってくれ、話を、」 「聞かない!!私の話を聞いて!」 ぶんぶん首を横に振ると、は一気に思いのたけをぶちまけた。 「なんでっ、なんで私に何も言わずに、そうやってまた一人で決めるんですか?! なんで私の前からいなくなったりするの?! 分からなかったんですか?私が、昨晩、どんな思いであなたのところへ行ったのか。」 「私のこと、私が答えを出すのを待ってくれてたんじゃないんですか? リーマスは自分勝手すぎる!私、もう振り回されたくないって言ったでしょ?!」 ボロボロと、の瞳から涙がこぼれ落ちた。 そんな彼女を、ルーピンは真剣に見つめていた。 「あなたが変身したとき、やっぱり…怖かった。でも、それ以上に、あなたを失うほうが怖いって分かったの。 たとえ一緒にいて傷つくことがあっても、私は…、あなたなら、あなたとなら信じてやっていけると思った。 だって、リーマスが私のこと信じてくれていると思っていたから。」 「…」 彼女は一度、深い呼吸をすると、ルーピンに切実に願うような眼差しを向けた。 彼の目も、と同じように少し潤んでいるように見えた。 「私が、あなたのために脱狼薬を作っては駄目ですか? もうあなたに人を傷つけさせたりしないし、誰にもあなたを傷つけさせたくない。 私だって、…力のない私だって、できることがあるでしょう?」 途切れ途切れの言葉を、はひとつずつ噛み締めながら言った。 真っ直ぐに、ルーピンを見つめながら。 「私も、あなたが私を守ってくれたように、あなたを守りたい。 リーマスが何であろうと、私は、あなたを愛してる。もう、二度と、失いたくないんです。 だから、お願い…」 ルーピンの襟元を掴んでいた手を緩め、は耐え切れずに泣きながら、 彼の肩口に額をつけ、か細く震える声で言った。 「側にいさせてください」 「」 ルーピンは、震える彼女の体を力強く抱きしめた。 「ごめん、君をこんなに苦しませてしまって、」 彼女の言葉が、彼の胸をこれ以上ないぐらい揺さぶった。彼女を抱く腕に力がこもる。 が息苦しそうに一度、ルーピンの名を呼ぶと、 彼は彼女の体を少し引き離し、その涙に濡れた瞳を愛しそうに見つめた。 そのまま、互いの唇が自然に重ねられた。 久しぶりに交わしたキスは、とても甘いものだった。 やがて2人の唇が離れると、リーマスは彼女を見つめながら、はっきりとした声で告げた。 「私も君を愛してる。 一緒にいたいんだ、。もう、離したくない。 私には、君しかいないんだ。それが、やっと分かった。」 「リーマス」 は涙を拭い、嬉しそうに眩しいぐらいの笑みを浮かべると、またルーピンに抱きついた。 彼もまた、彼女の背に腕をまわし、その温もりを感じながら愛しげに抱きしめた。 「ありがとう、」 やっと、その手がとれた。 「そういえば…、君が眠っていたベッドの横に置いてあった手紙、読んだかな?」 「え?手紙?」 きょとん、とした彼女の反応に、ルーピンは苦笑いを浮かべた。 「そうか、やっぱり。…あ、ちょうどよいところに来た。」 ルーピンと一緒にも立ち上がると、彼の見上げる先を見た。 青空の中を、ピンク色の翼を広げ、フィッチがのんびりとこちらに向かってきた。 ぽとり、と嘴から1通の封筒をルーピンの手に落とし、そのままフィッチは馬車の縁にとまった。 「ありがとう。―あとでダンブルドアにも礼を言わなくては。」 訳が分からない、といった表情のに向かって、ルーピンは困ったように微笑むと、 彼女にその手紙を渡した。は、しばし中の手紙を読むと、顔を赤らめた。 「…私、これに気付かずに、あなたを…」 先程ひっぱたかれて、少し赤くなっているルーピンの頬を、は申し訳なさそうに見上げた。 「いいんだ。疲れてる君を起こすのは悪いと思ったけど、ちょっと回りくどすぎたかな。」 そう言って、彼は少し自嘲気味に笑った。 封筒の中には、まだ何か入っているようで、はそれを手のひらにあけた。 そして目を輝かせた。 「…これ…」 封筒から転がり出てきたのは、ひとつの指輪だった。 シルバーに綺麗で繊細なレリーフが飾られたもので、陽の光を浴びてキラキラと輝いていた。 感動しながらも、はルーピンを見上げ、少し不服そうに言った。 「こんな大事なもの、なんで手紙と一緒に?」 「いや、違うんだ。これは…その、ちゃんとしたのは、君と一緒に見て選ぼうと思ってたから…」 眉を寄せるに、こういうことは初めてだったのか、予期せぬ事態だったのか、 ルーピンは頬を染めて、うろたえるように答えた。 そして、少しの間を経て、気持ちを決めた。 「そうじゃない、最初にこう言いたかったんだ―」 ルーピンは、改めてに向き直ると、真っ直ぐ彼女を見た。 彼の瞳には、もう今までのような、寂しさや切なさは消えていた。 ただその瞳に映るのは、愛しいだけ。 彼女の薬指にその指輪をはめ、自分の手をそっと重ねると、ルーピンは言った。 「、結婚しよう」 ルーピンの大好きな、幸せそうな、優しいその微笑を浮かべて、 はゆっくりと頷いた。 もちろん、彼女の答えは、ひとつしかない。 「はい」 (2007.10.18) まさかプロポーズまで書くことになるとは思わなかったのですw お気に召しましたらお願いします(*^-^*)→  web拍手 web拍手back / home / next |