|
「本当に残念じゃのう。」 ダンブルドアと握手をすると、彼はに微笑んだ。 「どうもありがとうございました。校長先生。」 学期末最後の日の翌朝、は職員室で、お世話になった先生方に挨拶をした。 「、しっかり、頑張るんですよ。」 マクゴガナルに抱きしめられてそう言われ、思わずは泣きそうになった。 「はい、先生」 教師と教師、というよりも、やはり、教師と生徒の別れのようだった。 マクゴガナルも涙もろく、ハンカチを出すと涙を拭った。 は一足先に辞職したルーピンと同じように、ホグワーツに別れを告げることにした。 これまでいた魔法省に戻り、今自分が何をしたいのか、しなければいけないのかを見つけたからだ。 「それにしても、よかったのう。 やっと、答えが見つかったようじゃ。」 満面の笑みでが頷くと、ダンブルドアは彼女を見守る瞳を細めて、願う気持ちを込めて言った。 「幸せになるんじゃよ、」 「はい」 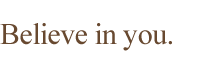 第40話 HOME 先生方一人一人と握手をし、は職員室を出た。 でも、まだ別れを告げていない人がいた。一番、感謝している人が。 ―今一番、会いたい人が。 「スネイプ先生」 その教室に足を踏み入れると、片づけをしていた彼は振り返り、を見た。 あの一件から、まだ一度も言葉を交わしていなかった。 「あ、あの、…その、お聞きになっていると思いますが、私、今期で辞めることにしたんです。」 少し気まずそうにが話し出すが、スネイプは顔色ひとつ変えず、ただじっと彼女を見つめていた。 「…そうらしいな」 そしてまたすぐに視線を戻し、彼は手を動かし始める。 「先生には、たくさんご迷惑をおかけしてしまって、本当に、…申し訳ありませんでした。 でも、とても感謝しています。…それを、伝えたくて…」 背中を向けたままの彼は、まるでまだ怒っているように思えて、は困ったように眉を寄せた。 どうしようか。このまま去っていっても、わだかまりが残るだけのようだし。 でもこれ以上、彼に聞いてもらえるような言葉は見つからない。 「お前がいなくなってせいせいする。」 がその場に佇んで迷っていると、ぽつり、とスネイプが呟いた。 思わず、彼女は顔を上げて彼を見た。 「―面倒な奴だ。生意気に口答えはする、我輩に杖は向ける、 挙句の果てに、ルーピンとつるんで辞職する…信じられんほど愚かだ。」 今までの行いを思い出して、は顔を歪めた。 でも、最後の彼の声は、違う響きを持っていた。 「…だが、勿体無いな」 と視線が合うと、スネイプは、僅かに微笑んだようだった。 「スネイプ先生!」 彼女はその気持ちを抑えられなくて、駆け寄って、スネイプに抱きついた。 持っていた薬瓶が床に落ちて割れ、彼は非難の声をあげた。 「…!」 「ありがとうございますっ、スネイプ先生。ありがとうございます…」 何度もその言葉を繰り返して、はスネイプの胸に顔をうずめて泣いた。 スネイプは何かを諦めて、泣きじゃくる彼女を見下ろした。 彼からに触れることはなかったけれど、 スネイプは今まで見たことのないような優しい眼差しで、 彼女が泣き止むまでただずっと、見守っていた。 揺れるバスの中で、は生徒たちから受け取った、たくさんのカードに目を通していた。 ハリーやロン、そしてハーマイオニーからのカードもあった。 "またいつか会えますように" "手紙書きますから、返事くださいね!" "いつでもホグワーツへ戻ってきてください。待ってます" どれも心温まるものばかりで、彼女の顔が自然に綻ぶ。 「わ、何これ」 "新婚家庭にお邪魔させていただきますので。 どうぞご覚悟の上、お待ちくださいますよう" ふざけた口調でおかしなことが書かれているものだから、はフフッと笑った。 フレッドとジョージからだった。 思い出すと、生徒たちが可愛くてしょうがなかった。 本当に、また会える日がきたらいいな、とは切に思った。 郊外をかなり進んだところで、はバスを降りた。 民家もまばらで、草原や青々とした木々しかない殺風景な場所だったけれど、 夏の青空に、やわらかな風が舞う、気持ちのよい場所だった。 懐かしい匂いがする。 均された小道を少し歩いたところで、前方に一軒の家が見えた。 は感慨深げに、立ち止まってその古い家を見た。 久しぶりに目にする、我が家だった。 帰る日がくるなんて、思ってもみなかった。 そこには、両親と幼い自分の記憶しかなくて、それは思い出すたびに悲しいものだったから。 ―でも、今は違う。 ふと、その家の玄関から、誰かが出てきた。 日にあてていた古い家具を、家の中へ入れるところだったようで。 暑い日差しに、腕で額の汗を拭うのが見えた。 彼が何気なく顔を上げて周囲を見渡したとき、彼女の姿を見つけた。 その表情が、微笑みに変わる。 は荷物をひきずりながら、急ぎ足で門まで歩いた。 ガタガタと鳥籠が音を立てて揺られ、中にいたフィッチが不機嫌そうに鳴いた。 「リーマス!」 門を開けて出てきた彼はにっこりと笑うと、荷物を置き駆け寄ってきた彼女を、しっかりと抱きしめた。 「おかえり、」 大切な人がいる。 その人が待っている家がある。 それが、こんなにも幸せで素敵なことなんだって、知らなかった。 ここまでくるのに、なんて回り道をしてきたんだろう。 でも、どれもかけがえのない道のりだった。 あなたが私を信じてくれたから、私も自分を信じることができた。 そして、あなたを信じることができた。 「ただいま」 だからきっと、この先も一緒に歩んで行ける。 私たちの新しい道が、今、ここから始まろうとしている。 Believe in you. The End. (2007.10.18) →→あとがき&アンケート お気に召しましたらお願いします(*^-^*)→  web拍手 web拍手back / home |