|
しばらくして意識が戻ると、まだ胸の痛みが残っていた。 霞む視界でぼんやりと辺りに視線を移すと、まだ先程いた場所と変わっていなかった。 ルーピンの部屋だ。スネイプが去って、どれぐらい時間が過ぎたのだろうか。 横たわったままの姿勢で、後ろ手に縄で縛られた腕をほどこうともがくが、びくともしない。 彼らはどうなったのだろう。無事だろうか。 もしルーピンやブラックに何かあったりしたら、と思うと、 は情けなさと同時に、自分の非力さが悔しくなった。 『でも、リーマスは闇の魔術に対する防衛術の先生だし、…きっと大丈夫。』 不安を打ち消すように、そう自分を説得させると、は床に転がっているはずの杖を探した。 けれども、彼女の杖は見当たらなかった。 『どうしよう』 きつく縛り上げられた腕を、渾身の力でほどこうと奮闘したが、ほんの少し緩んだだけだった。 『何か縄を切れるものが…』 目についたのは、テーブルの上に置いてあったティーセットだった。 怒るかな、と思いながらも、はその近くまで這いながら移動して、やっとのことで上半身を起き上がらせると、 ティーセットが置かれたトレイの端を口に銜え、そのまま力を入れて口先から体重をかけて押した。 案の定、ガシャンという音をたて、それらはテーブルから床に落ち、 繊細なカップやティーポットは割れ、いくつもの破片が辺りに散らばった。 は大き目の破片を、恐る恐る後ろ手に掴んだ。 肩越しに自分の手首を見つめ、乾いた唇を噛んだ。 失敗する訳にはいかなかった。指の間に汗が滲むほどに、彼女は緊張していた。 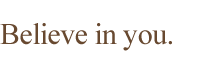 第37話 満月 クルックシャンクスに続いて、窮屈なトンネルから這い上がると、 ルーピンは右腕に繋がれているペティグリュー、そしてロンがその後から出てくるのを待っていた。 その時、 「リーマス!!」 振り返ると、校庭を、息を切らせながらが走ってくるところだった。 「…?!」 トンネルから顔だけ突き出して、ロンも目を丸くして、近くで立ち止まった彼女を見ていた。 「…地図を見たら、上手くいった、みたいだったから…、 ごめんなさい、私のせいでスネイプ先生が…」 ハアハア、と肩で息をしながら、はルーピンを見つめながら言った。 彼は彼女を優しい眼差しで見つめ返し、首を横に振った。 「よかった、君が無事で。」 は少し嬉しそうに一度頷くと、ルーピンの腕に手錠で繋がれている、ペティグリューを見た。 彼はと目が一瞬合うと、ぱっと怯えるように視線を逸らした。 「ロン!大丈夫?」 痛む足をひきずりながら、ロンはルーピンとの手を借りてトンネルから出た。 「先生は全部知ってたの?」 「ええ。」 「…ルーピン先生のことも?」 少し驚いた様子でロンに聞かれ、は微かに笑みを浮かべながら答えた。 「そうよ。」 その後、ロンに向けられた視線を気まずそうにかわすと、ルーピンは急かすように言った。 「さあ、行こうか。あとが突っ掛えてるよ。」 ハーマイオニー、そして奇妙に宙吊りにされているスネイプの後に、 ハリーとブラックがトンネルから這い出てきた。 ブラックはに気付くと、彼女に向かって笑いかけた。 「君のおかげだよ。ありがとう。」 「いいえ、私はほとんど力になれなかったもの。」 は少し肩をすくめて微笑んだ。ブラックの横にいるハリーの表情は明るかった。 スネイプには気の毒だったが、全て上手くいったのだと思うと、も嬉しくなった。 しばらく校庭を歩いていると、突然、空を覆っていた厚い雲が途切れた。 月明かりに照らされ、それぞれの影がぼんやりと地面に落ちた。 ふいに先頭を行くルーピンたちが立ち止まった。 後方からそれに気付いたは、眉を寄せた。空を見上げれば、そこにはキラキラと輝く満月があった。 「リーマス、まさか…!」 の横でブラックも立ちすくみ、腕をさっと上げてハリーとハーマイオニーを制止した。 ルーピンの黒い影が、ガタガタと震えだすのを見た。もハリーたちも、突然訪れた状況に動けずにいた。 「逃げろ!早く!」 ブラックが叫んだ。しかし、ロンがペティグリューとともにルーピンの側にいるため、ハリーは動けなかった。 「ここは私に任せて逃げるんだ!、ハリーたちを連れて行け!」 名前を呼ばれたは、はっと我に返りハリーとハーマイオニーの手を掴んで駆け出そうとした。 それでも、ハリーはその場から動こうとしない。むしろロンのほうへ行こうとする。 「ハリー!」 は大声でハリーに訴えながらも、彼の視線の先を振り返って見た。 ルーピンの影が、みるみる獣の姿に変わっていった。 の鼓動は一層早くなり、ハリーたちを掴んでいた手が震え始めた。 それに気付いて、ハーマイオニーはを見上げた。月明かりに照らされた彼女の顔は、恐怖で強張っていた。 さきほどまで側にいたブラックは、大きな黒い犬の姿に変身し、 狼人間の首に食らいついて後ろに引き戻し、ロン、ペティグリューから遠ざけた。 二匹はそのまま牙と牙をぶつかり合い、お互いを引き裂き合い戦っていた。 「あっ!!」 ハーマイオニーが声をあげたと同時に、バンという音と白い光が前方に現れた。 ペティグリューがルーピンの杖を持ち、ロンが倒れて動かなくなっていた。 「「ロン!!」」 「エクスペリアームス!」 ハリーの呪文で、ペティグリューの手からルーピンの杖が吹っ飛んだ。 「動くな!!」 ハリーがの手を振り解き、前方に走り出したが遅かった。 ペティグリューの姿は一瞬にして視界から消え、かさかさと草むらを走り去る音が聞こえた。 それと同時に、高く吠える声が聞こえ、狼人間が禁じられた森へ疾駆していった。 「シリウス!あいつが逃げた!ペティグリューが変身した!」 ハリーが叫ぶと、ブラックはルーピンとは違う方向へと校庭を駆けていった。 ハリー、たちは、急いでロンの周りへ駆け寄った。 「先生、ロンは?」 「…錯乱している状態だけど、意識はあるから大丈夫よ。 マダム・ポンフリーに気付け薬をもらわないと。」 がロンの目を覗き込みながら言った。 「城に戻りましょう。彼を手当てして、校長先生に話さなくては…」 視線をふとロンからはずした時、は草むらに黒いものが広がっているのに気付いた。 それは血だった。彼女の背に冷たい汗が走る。 『リーマス…』 その時、ブラックが走り去った方角から、犬の悲痛な鳴き声が聞こえた。 「シリウス」 ハリーは一旦暗闇を見つめながら躊躇したが、すぐに鳴き声の聞こえる方へ駆け出した。 「あっ、待ちなさい!」 の制止も聞かず、ハリーは校庭を駆け出した。ハーマイオニーもその後に続いた。 「ハーマイオニー!」 残されたは、ロンの顔を見下ろして一瞬どうしたらよいか迷ったが、 彼の握っていた杖を借りて担架を作り出した。 ちらり、と宙にぶら下がっているスネイプを見て、彼にかかっている魔法を解いた。 途端にスネイプはどさっと草むらに落ちた。そこへ駆け寄る。 「先生!起きてください、スネイプ先生!」 ぐったりしていたスネイプの頬を何度か叩くと、苦い顔をしながら彼が目を覚ました。 「…?!お前、どうやって、」 がばっと起き上がり、周囲を見回してスネイプは眉間の皺を寄せた。 草むらには担架に乗った、意識がないロンしかいなかった。 「ペティグリューが逃げました!ブラックも、ハリーたちも一緒です。湖の方角へ」 ハリーたちが去っていった方を指差し、は叫んだ。 スネイプは立ち上がり、彼女が指差すほうを見つめた。状況を掴むのに少し時間がかかった。 も立ち上がると、ロンの担架を城へと移動させるよう呪文をかけ、 守護霊を作り出しその行く手へ飛ばした。彼女の守護霊は、大きな翼を持つ鳥の姿をしていた。 「待て、お前はどうするつもりだ?」 「私は…、彼が、リーマスが変身してしまったんです。怪我を負ってる。 このまま放っておけません。」 「馬鹿な。そんなもの人狼の奴は慣れっこだろう。お前が行ってもみすみす食われに行くだけだ。」 スネイプが正しかった。それでも、は胸騒ぎがして、落ち着かなかった。 ルーピンが目の前で変身をしてしまって、とても恐ろしかったのに。 でも、それ以上に恐ろしいことがある。 あの晩の記憶が、の頭の中によぎった。 「私はこれ以上大切な人を失いたくないんです! このまま、彼が戻ってこなかったら、私は一生後悔する」 震える声でそう言うと、は拳を握り締めた。 真っ直ぐな、切実な彼女の瞳を見ていたスネイプは、視線をそらすとつぶやくように言った。 「勝手にしろ」 が森のほうへ行こうとすると、後ろからスネイプに呼び止められる。 「」 スネイプが何かを草むらから拾い、のほうへ投げた。 何も見えなかったが、反射的に出した腕に、重さが加わった。その感触は布のようだった。 「ポッターのものだ。それをかぶれば姿は見えない。」 そう言われ、は手元にあるものを見つめた。彼女の腕から先は視界から消えていた。 「先生、」 がスネイプに礼を言おうと顔を上げたが、彼は既にその場を後にしていた。 その後姿を見つめ、胸の内で礼を言うと、も森へ向かい走って行った。 (2007.10.17) スネイプ先生を行かせてどうする!と後から気付いたんです…しょうがなかったんです(汗。 お気に召しましたらお願いします(*^-^*)→  web拍手 web拍手back / home / next |