|
「ネズミ?」 「そう、あなたのペットって、確かネズミだったわよね?」 大広間から出て行くところで、ロンはに呼び止められた。 彼女の質問に、ロンも隣にいたハーマイオニーとハリーも、なんだか気まずそうな顔をした。 「まぁ、最近まではそうだったんですけど…」 チラリと一瞬視線をハーマイオニーに送ったあと、ロンはさっぱりとした口調で言った。 「あいつも年だったし、もう死んじゃったんですよね。」 「えっ!」 驚くに、横にいたハーマイオニーは軽く頭を下げると、その場を去ってしまった。 「まさか、ほんとに?」 眉を寄せる彼女に、ロンとハリーは頷いた。視線は去っていった友を追いながら。 「確かじゃないんですけど、どうやらハーマイオニーのペットの猫が食べちゃったみたいで。」 「…猫って、もしかしてオレンジ色の猫?」 「はい。」 2人に挨拶をしてその背中を見送ると、はとても脱力した。 ネズミが、ペティグリューだと言われていたネズミが死んでしまっては、 どうにもならないではないか。 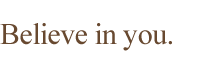 第34話 すれ違い 早速ペティグリューを探そうと思っていたのに、出鼻をくじかれたようだった。 がこのことを、フィッチに託してブラックに報告すると、彼からの返事がすぐに返ってきた。 あの猫が食べる訳がない。ペティグリューは食べられたフリをして逃げているだけだと。 ため息をついて、は彼からの羊皮紙を杖の先を振って燃やした。 「猫が見つけられないものを、私にどうやって見つけろって言うのよ。」 ホグワーツは広大な敷地を有している。そこをくまなく探すのはとても時間がかかる。 おまけに相手はネズミの姿をして動き回っている。他にも普通のネズミなんて古い建物だから、たくさんいるはず。 見分けもつかない。 それでも、空き時間を見つけては、は城中の人気のない場所に罠をはりめぐらせたり、 何匹かの頭の良い猫を借り、城中を探させたりした。最も、効果はあまりなかったが。 月も変わり、温かい日が続くようになった。半ば、はネズミ探しを諦めかけていた。 いつまで経ってもペティグリューは見つからない。 ただのネズミばかりが見つかっていて、よほど上手く隠れているのか、または初めからペティグリューなどいないのか。 はただ騙されているのかもしれない、と薄々感じ始めていた。自分を騙したところで何にもならないだろうけれど。 月例の職員会議の席で、は何気なく、ルーピンの背中を見た。 今でもなかなかその存在に気付いても、視線を向けることはできなかった。 目を合わせるのは怖かったし、それは彼の一挙一動にまだ心が乱されてしまいそうだったからだ。 避けることには大分慣れてきた。これが、今自分にできる最善の策だとは考えていた。 彼の姿を視界に捉えながら、ふと、は思った。 ルーピンなら自分の知らない魔法もたくさん知っている。経験も豊富だ。 探し人を見つけるなんて、そんなに苦労しないだろうと。 そう、きっとあっという間に… 「……あっ!!!!」 いきなり大声をあげたものだから、教員たちが一斉にのほうを振り返った。 慌てて口を手で抑える。 「どうかしましたか?教授」 「いいえっ、どうぞ続けてください!」 顔を赤くした彼女は、ドキドキと緊張しながら、机の上に視線を落とした。 『そうだ、なんで早く気付かないんだろう。バカだわ、私。 あるじゃない、ペティグリューを見つけ出す方法が!』 思い立ったらすぐ行動する。 でもこのときばかりは、さすがのも気が引けた。 「…あの、」 先生方と廊下で別れたところを見計らって、は恐る恐るその背中に声をかけた。 心なしか、その声も手も震えていた。どうしようもないくらい、緊張していた。 「どうかした?」 ルーピンは自室の前で、少し気まずそうに笑顔で振り返った。優しい声音は、彼女を気遣うようだった。 彼の視線が降りてくると、は慌ててそれから目を逸らした。 「ちょっと、お願いがありまして…」 「私に?」 「はい。あの、…地図を、お借りできないでしょうか?」 下を向いていたは、ルーピンが淡い期待の表情から一転、落胆したのに気がつかなかった。 彼は周囲を見渡した後、彼女を自室に招き入れた。 「理由を聞いてもいい?」 少し低くなった声のトーンに、はますます逃げ出したくなった。 「生徒の、ペットを探してるんです。城にいる間に逃げ出してから、もうここ数ヶ月見つからなくって。 あまりにも落ち込んでるから、私も協力しているんですけど。情けない話、なかなか上手くいかないんです。」 「ああ、だから最近あんなにあちこちに罠が置いてあるのか。」 ルーピンが笑った気配がして、それから彼は自分のデスクへと向かった。 はほっとして、ルーピンがデスクの2番目の引き出しから、古びた羊皮紙を取り出すのを見つめた。 まさかこんなに簡単に貸してくれるとは思わなかったから。勇気を振り絞ってよかったと思った。 「ありがとうございます。」 がやっと視線を彼に向けて、にっこりと微笑んだ。 彼女に忍びの地図を手渡そうとしたルーピンは動きを止め、表情を曇らせた。 「本当の理由はなんだい?」 「え?」 「私に嘘をついて、この地図を使うのはどうしてかと聞いてるんだ。」 はぎくりとして、一瞬ためらってしまった。 「嘘だなんて、」 「また君は自分の身も省みず、危険なことをするつもりじゃないのか?」 彼の口調は決して彼女を責めるものではなく、むしろ案じているようだった。 しかし、には何もかも見透かされているように思えて、追い詰められた気分になった。 「私が何をしようと、もうあなたには関係ありません」 思わず発してしまった言葉に、彼女ははっとしてルーピンの顔を見た。 その顔はいつもより一層蒼白に見えた。 が次の言葉を探すより先に、ルーピンは少しかすれた低い声で言った。 「それでも、私は君のことが心配なんだ。」 は視線を落としたまま、その言葉に目を見開いた。 「自分勝手なことを言っているのは分かってる。 でも、あれからずっと、君に謝りたかった。」 見上げれば、熱のこもった、切ない瞳が彼女を見つめていた。 それは、には信じられないようなことだった。 まさかそんな瞳でまた自分を見てくれるとは、思ってもみなかったのだ。 そうだ、別に嫌われているわけじゃなかったのに。 の胸が急に高鳴りだして、腰の前に組んでいた両手が震えていた。 それが分かったのか、ルーピンは空いているほうの手で、震える彼女の手にそっと触れた。 突然、その温もりが伝わってきて、は身動きがとれなくなった。 彼との距離が縮まる。 「、…私はまだ、」 きっと待ち望んでいた言葉が聞けるというのに、 またあなたが私に触れてくれたというのに、 私は、 「だ、だめ」 ルーピンの動きが止まった。 は潤んだ瞳を湛えて、泣いているのか、微笑んでいるのかも分からないような 曖昧な表情をして言った。 「あなたは、私のことを思って離れてくれたんでしょう?それが、正しかったんですよ。 私は一緒にいたら、今みたいに、またあなたに嫌な、辛い思いをさせてしまうし…、」 嘘。 どうしたらいいか分からない。 何が正しいのかなんて、本当は分からない。 ただ、 「私だって、もう…あなたに振り回されたくない…」 怖い。 もとはといえば、自分のせいなのに。 突き放されて、拒絶されて、傷ついて、 自分を保つのが精一杯で、あなたの気持ちさえもう考えられなくなってしまった。 こんな状態でいても、いいはずがない。 一緒にいても、またお互い傷つくのだったら、一緒にいないほうがいい。 もうこれ以上傷つくのが怖くなってしまった。 「」 触れていた手に少し力を込めると、ルーピンはゆっくりと、優しい声で言った。 「私は正しくなんてない。何が正しいのかなんて、誰にも分からないんだよ。 大切なのは、自分たちがどうしたいかということだって、今になってやっと気付いたんだ。 私は君がどんな風に思ってくれてるか、どんなに努力しているかを無視して君を傷つけた。 ひどいことをした―すぐに許してくれなくてもいい。」 「だが…、どうか、もう一度考えてくれないか。 私はもう、逃げたりしないから。」 が瞬きをすると、ぽたりとルーピンの手の甲に、雫が落ちた。 困惑した表情で、それ以上話せなくなってしまった彼女の頬に伝う涙を、 ルーピンはそっと拭い、囁いた。今すぐに返事をしなくてもいい、と。 廊下を一人歩くの頭の中は、 彼が手渡してくれた地図のことも、教えてくれた呪文もうわの空で。 ただルーピンの言葉が、手の温もりが、優しい声が、 自分のことを想ってくれる懐かしい瞳が、 彼女の胸をしめつけていた。 (2007.8.30) 長い。大変でした。似たもの同士な2人なんです。 お気に召しましたら(*^-^*)→  web拍手 web拍手back / home / next |