|
が4度目にその犬を見たのは、クィディッチの試合の前日だった。 グリフィンドールがもしスリザリンに勝てば、クィディッチ杯獲得ができるという大事な試合だった。 数週間前からふたつの寮の熱気は高まっていくばかりで、それもこの2、3日がピークだった。 グリフィンドール生とスリザリン生が、夜中に口論しているのを聞きつけ、 生徒たちに注意をしている矢先、校庭を歩く黒い影を見た。 外も暗闇で、あやうく見失ってしまいそうだった。 けれどもその時、犬は猫と連れ立って歩いていた。 そのオレンジ色の猫に目をひかれた。誰かのペットだろうか。 2匹が暴れ柳の方向へ向かうのを見て、は思わず息を呑んだ。 なぜ、また危険を冒してまで校内へ忍び込んでいるのだろうかと。 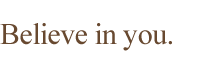 第33話 無実 『うわ、怖い…』 杖の先で行く手を照らし、は少し足が竦んだ。 細いトンネルは、明かりの届かないところは真っ暗で、先が何も見えない。 でも、あのルーピンの持っていた地図を見る限り、この先はホグズミードにつながっている。 彼がいたら、こんなことするな、とまた叱られると思い、は小声で呟いた。 「もう、関係ないの」 叫びの屋敷は、月明かりだけで部屋の中がやっと見れるぐらいだった。 相変わらず廃れた、気味の悪い雰囲気は変わっていなかった。 明かりを消した杖を手にきつく握り締めながら、は右手の扉から続くホールを見た。 足音を忍ばせて近づくと、ゴロゴロと、太い猫の鳴き声が聞こえた。 その猫の隣には、あの黒い犬が座っていて、光る瞳でを見つめていた。 まるで彼女を待っていたかのように。弱々しげに尻尾を振って、犬が立ち上がった。 「動かないで!!」 素早く杖の先を向けると、は叫んだ。 こんな時間に、こんな不気味な場所に一人でいるのに、不思議と彼女に恐怖はなかった。 「…シリウス・ブラック」 ぴくん、とその黒い犬が反応を示した。 「あなたが変な真似をしたら、今すぐ縛り上げて吸魂鬼に引き渡すわ。 でもその前に、私はあなたに聞きたいことがあるの。 もし、あなたも私に話す気があるなら…正体を、ここで現して。」 もしこれが、本当にただの犬で、ブラックではなかったら、本当に自分はマヌケだ。 そんなことがの頭をよぎった。そのほうがずっと平和だ。 でもそのの期待を裏切るように、黒い犬はつい、と首を下げたかと思うと、 一瞬にして首や手足が伸び、目の前にやつれた、囚人服の男が現れた。 は思わずたじろぎ、その場から一歩引いた。 「…君には本当に驚かされる…」 久しぶりに聞く声は、相変わらすしわがれていたままだった。 ブラックは口角を上げ、暗い目でを見た。以前よりも、彼女に対する警戒心は薄れているようだった。 「私の正体を知っていながら、毎日のようにあのふくろうを遣わしていたのか?」 「はじめは知らなかったわ。あなたが動物もどきって気付いたのは最近よ。」 「ではなぜ誰にも言わなかった?なぜ一人でここまで来た? 私をアズカバンを脱獄した囚人と知っているんだろう。」 ブラックの顔には、苦笑いが浮かんだ。 「…ああ、それとも、リーマスと組んで私をはめるつもりか?」 「彼はそんなことしないわ。あなたの正体だって、私が聞くまで黙ってた。」 は首を振って否定すると、少しためらってから、言った。 「…本当に、あなたは友人を殺したの?」 彼女の静かな声に、ブラックの目が大きく見開かれた。 「私はあなたがハリーの命を狙っているようには思えない。 あなたがここにいる本当の目的は、何?」 ブラックは、ショックで口を開けたまま、を見つめていた。 こんな言葉を犯罪者の自分に、犯罪者にされた自分にかける人間が、いるはずはなかった。 12年前、―家族、友人でさえも。 「君は、私の話を聞いてくれるのか」 震える声でやっとそう彼が答えると、は杖を向けたまま頷いた。 「話の内容によっては、私がどうするか分かるわね? 生徒が今でも危険に晒されているのだったら、私はあなたを許さない。 だから、はっきりしておきたいの。」 ブラックの話は信じ難いものだった。 彼は殺人など犯していないこと、ピーター・ペティグリューという友人が本当は犯人で、 入れ違いになり、ブラックは無実の罪で囚われたのだと。 しかし、その証人となるべき人が誰もいない。昔に流れたニュースでは、ペティグリューはブラックに殺されたとされていた。 ブラックが脱獄してまでホグワーツにやってきたのは、その死んだペティグリューが、本当は生きていて、 今ハリーの側にいるから、彼を捕らえるためだというのだ。 「おまけに、そのペティグリューが、ハリーの友達のペットのネズミ…?」 疑いの眼差しを変えないまま、はブラックに言った。 「リーマスから聞いているんだろう、奴も私たちと一緒に動物もどきになった。 奴がネズミの姿に変わるのを、私は何度も見ている。だからあのペットに間違いはない。」 なかなか上手く伝わらない焦りと苛立ちが、ブラックの顔に表れていた。 はそのまま、何も言わずしばらく黙っていた。 杖の先をブラックに向けた状態で、考え込むようにたまに視線をさ迷わせた。 ブラックは、祈るような気持ちで彼女を見つめていた。隣で座っていた猫は、気持ち良さそうに床で丸まって眠っていた。 「分かったわ。とにかく、そのペティグリューが本当に生きているのか見つけ出さないと、ダメってことね。」 沈黙を破って、ははっきりとした口調で言った。 ブラックは肩の力を抜いて、ほっとしたようにため息をついた。 「私はまだ完全にあなたを信じたわけじゃないわ。」 「今はこれだけで十分だ。ありがとう。」 くぎを刺すように言った彼女の言葉に、やせ細った顔に、微かに笑みを浮かべたブラック。 その表情を見て、内心は思った。彼はやっぱり無実なのかもしれないと。 「…あなたこそ、私をこのまま信じていいの?すぐに吸魂鬼を連れて戻ってくるかもしれないわよ?」 来た道へと続く穴に足を踏み入れ、はブラックを振り返り言った。 彼は先程と比べ、幾分か軽くなった口調で答えた。 「君は私の命の恩人だ。信じられる人がいるとすれば、今は君しかいない。」 はじっとブラックの瞳を見つめた後、トンネルの先を行く猫を追いかけてその場を去った。 もう明け方だというのに、彼女は目も、頭もさえていた。 先程まで聞いていた信じられないような話。平静でいられるはずがない。 彼の話が本当ならば、 彼が本当に無実なのならば、 急がなくてはならない。 人の命がかかっているのだから。 (2007.8.19) 先生たち出てきませんでした。思いもよらぬ展開に。 お気に召しましたら(*^-^*)→  web拍手 web拍手back / home / next |