|
「わー!ちょっと止めなよ、飲みすぎだってば!」 「止めないでっ、たまには飲んだっていいでしょ! 学校にいたんじゃ全然飲めないし、グチを聞いてくれる人だっていないしっ」 新たにワインのボトルを開け、グラスに注ぐ彼女を慌てて止める友人の姿。 店の奥の席で、何時間にも渡るやりとりを、店主のマダム・ロスメルタが笑いながら見守っていた。 「あんたそんなこと言って、お酒弱いくせに。学校に戻れなくなるよ?」 「いっそのことそうなってくれたほうが有難いわ。」 「、教師の自覚ある?」 「ああ、もう!今は教師とかそういうのは関係ないのよ、トンクス!」 「あら、そうですか」 顔を赤くして膨れっ面のの額を、トンクスはペチペチと叩いてからかった。 ピンク色のショートヘアの彼女とは、学生時代からの親友だった。 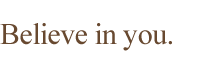 第32話 ラスト・チャンス 久しぶりに時間ができたから会おう、とパブ『3本の箒』に呼び出されてきてみれば、 の話を延々と聞かされ、お酒に付き合わされてしまったトンクス。 以上に忙しい闇祓いの彼女だが、嫌な顔ひとつせず付き合ってくれた。 「まったく、あんたたちって面倒くさいよね。」 「面倒くさい?」 大分酔いがまわって、とろん、としているに、トンクスは呆れた顔で言った。 「だってお互い好き合ってるのに、なんで別れたりしたの? 自分の気持ちに素直に従えばいいのに。」 「…だって、しょうがないんだもん。それができたら苦労しないわよ。」 立てた腕に顔を乗せ、はぽーっとグラスを見つめたまま言った。 その横顔は、とても寂しそうだった。 「ほんとにしょうがないの?ね、、諦めるの早いんじゃないの?」 「私だって諦めたくなかったけど、…もう何したってダメなの。 リーマスが私のためを思ってそう望んでいるなら、私はそれを尊重したい。」 はまた少し涙声になったかと思うと、机に突っ伏してしまった。 「…も〜、人がやっと諦める決心がついたっていうのに…」 ボソボソ、といじけた声が聞こえる。 そんな彼女の頭をよしよし、と撫でてあげながら、トンクスはお人好しのに対し、小さいため息をついた。 『なにが尊重だよ。』 「はいっ」 「…は?」 ルーピンは、目の前に差し出されたものを呆然として見つめた。 「受け取ってくださいよ、このお荷物。」 「ちょっと、君の守護霊が言ったことと随分違うじゃないか。」 こんな吸魂鬼もうろついて見回っている夜更けに、見知らぬ守護霊に呼び出され、城の玄関に息をきらせながら来てみれば、 会ったことの無い派手な頭の若い魔女が、を背負ってルーピンを待っていた。 差し出されたお荷物の当の本人は、ぐったりと気持ち良さそうに寝入っていた。 「よかった。ほんとは来てくれないかと思ってたからさ。 私これから仕事に行かなきゃいけないから。…こんな夜じゃなきゃ先生たちに挨拶するのになぁ。」 そう言いながら、トンクスはルーピンに背を向け、強引にを落とそうとした。 「おい!」 ルーピンは慌てて、彼女の背からずり落ちるを受け止めた。 「言っておくけど、飲ませたのは私だけど、飲む原因はあなたなんだよ?」 振り返り、トンクスはにかっと彼に笑いかける。 「私、ルーピンさんのことあんまり知らないけどさ。 あなたが思い込んでるほど、人狼ってこと知っている人は、そのこと気にしてないと思うよ。 知っていてそれでも側にいるのは、みんなあなたが好きだからだよ。」 「……」 「あなただって好きで人狼になった訳じゃないし、だって好きで人狼が怖くなった訳じゃないでしょ? この子は、それを何とかしようとしてるのに。 …ルーピンさんも変わらなきゃ、自分のことだって、この子のことだって、幸せにできないんじゃないかな。」 爽やかにそう言うトンクスを、ルーピンは雷に打たれたような顔をして見つめた。 「ラスト・チャンス。 にまだ気持ちがあるんだったら、彼女の幸せって何か、もう一度考えてみてください。」 笑顔を崩さず言い終わると、じゃあよろしくと手を振って、トンクスは敷地の外で姿を消した。 何も言えなかったルーピンと、大切な親友を残して。 は自室のベッドに横にされても、まだほんのり赤い顔をして、寝息を立てていた。 彼女を1階から運んできたルーピンは、そんな彼女を見下ろしてため息をついた。 先程の魔女から言われた言葉が、頭を離れない。 自分勝手な感情に、惑わされる。そんな自分が嫌だった。 自分の思い込みだと、分かっていた。 私と一緒にいても、彼女は幸せになれないと、自分に思わせた。 のために、彼女を傷つけないために離れようと思った。 でも、本当は、それは彼女のためではなく 私自身が傷つきたくないから、自分に言い聞かせただけだったんだ。 最低だ。 彼女を傷つけたくないと言いつつ、一番私が彼女を苦しませている。 自分から遠ざけたのに、離れれば離れるほど彼女が愛しくなる。 が他の誰かと幸せになってくれることを願っているのに、側にいて欲しいと思ってしまう。 彼女を傷つけていながら、なんて我侭なのだろう。 自分でも、この感情をどうしたらいいのか分からない。 人を、こんなに愛したことはないから。 (彼女の幸せって何か、もう一度考えてみてください) の寝顔に残る、涙の跡を見て、眉を寄せる。 (私は、一緒にいたいと今でも思ってる) 、 私も、君の側にいたい。 でも怖いんだ。 今まで人に忌み嫌われてきた私は、 君のその手をとるのが。 かけがえのないものを手に入れて、失うことが。 私と、君の未来を信じることが。 (ルーピンさんも変わらなきゃ) 「…その通りだな…」 赤の他人が分かるようなこと、なんで自分は分からないのだろうと、年甲斐もなく情けなくなった。 彼女に触れる資格なんてないのに、子供のように眠るその頬に、ルーピンはそっと唇を寄せた。 懐かしい、温かい感覚が、胸を締め付ける。 目の前にいるが、とても美しくて、尊くて。愛しくて堪らなかった。 彼女の手をとれるようになりたい。 もう遅すぎるかもしれないけれど。 (2007.8.3) やったぜトンクス!そして恋にとことん不器用な三十路の先生です。応援してあげてくださいねっ。 お気に召しましたら(*^-^*)→  web拍手 web拍手back / home / next |