|
嫌なことというのは、まるで呼び寄せるように立て続けに起こることがある。 珍しくダンブルドアに呼び出されたは、 受け取った厚い羊皮紙を、ぽかんとした表情で見下ろした。 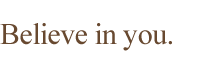 第31話 ピリオド 「…解雇要請?」 「さよう。もっとも、そんな紙切れは何の効力も持たん。 教職員や生徒の処分を決めるのはワシじゃからのう。」 そう言って、ダンブルドアは特にその内容を気にしていないのか、暢気に笑った。 それでも、にとっては胃が重くなるようなもので。 彼女の手元にある羊皮紙に書かれているのは、マグル学の教授、・の解雇要請だったからだ。 出所はホグワーツ魔法魔術学校理事会。昨年、生徒に暴行を働いたことが原因だった。 理事会とつながりのあるマルフォイ氏が、影で糸をひいているのは明白だった。 「そう気を落とすでない、。わしはもちろんそんな要請に応じるつもりはないんじゃよ。 あの件はそこまで騒ぎ立てるものではないし…おっと、これは個人的な意見じゃが。 この時期に蒸し返してくるとは思ってもみなかったがのう。」 「すみません、校長先生。私、先日魔法省に行って、そこで…」 複雑そうな顔をして見上げるに、ダンブルドアは首を横に振ってから、微笑んだ。 「もちろんそれも聞いておる。あの場にいたアーサーからな。 君は気にすることはない。わしは君にはこの学校にいて欲しいんじゃ。生徒からの評判も良い。 教え子がここまで成長しているとは、わしも鼻が高いんじゃよ。」 「ありがとうございます。」 はようやくにっこり微笑んで、恩師の優しい目を見上げた。 「そうそう、その笑顔じゃ。最近先生が元気がないと言って、生徒たちも心配しておった。」 「えっ」 生徒に心配されているとは思っていなくて、は未熟な自分が恥ずかしくなった。 「子供は大人が思っている以上に、よく見ているものなんじゃよ、。 君が笑顔になってくれるのを、みな心待ちにしておる。」 「…はい」 ダンブルドアの言葉は温かみを持っていて、父親がいたらこんな感じだっただろうかと、は思った。 少し泣きそうになる顔を隠すように、彼女はうつむいた。 そしてふと、以前から気になっていたことを思い出した。 「先生、私ひとつお聞きしたいことがあるんですが。」 「なにかのう?」 「ルーピン先生が人狼であること、私に隠していたのはどうしてですか? 私が警戒すると思いましたか?」 ダンブルドアは少しきょとんとした顔をすると、を見て言った。 「そんな風に思ってはおらんよ。これはわしの、ただの年寄りの勘じゃが…、 2人ならそれぞれが抱えている問題を解決できると思ったんじゃ。周りが余計なことを言わずとも。」 「でも、私たち…」 「大丈夫じゃ、。すぐに答えを出せなくても良い。 だからそう、思いつめないことじゃ。」 「…はい…」 ついには目に涙を溜めて頷くを、ダンブルドアは見守るように温かく微笑んだ。 そうだ。 このままじゃいけないって分かってる。 私には仕事がある。生徒たちもいる。 いつまでも落ち込んでなんていられないんだ。 でも、先生。 私にはどうしたらいいのか分からないんです。 ここにあの人といる限り、ずっとこの想いを胸に抱いたままだから。 この苦しさは、時間が解決してくれるのでしょうか。 校長室を出るときダンブルドアから受け取ったある一通の手紙。 は廊下を歩きながら、その封を切った。文面を読むと、はぁ、とため息をつく。 先程見た解雇要請のものとは、雰囲気が違い、温かい見慣れた文字で綴られている。 今回の件を心配してくれた元上司が、ダンブルドアに託した手紙だった。 『いっそのこと、魔法省に戻ってしまおうか』 がそんなことを考えて顔をあげると、運悪く、廊下の向こう側からその人が歩いてきた。 ルーピンが彼女に気付く前に、は顔を強張らせて下を向いた。 気付かないで、このまますれ違ってしまえばいいのに。 未だにこんな頑なな態度しかとれない自分が情けなかった。 「」 久しぶりに名前を呼ばれて、どきんと胸が高鳴った。 恐る恐るが見上げれば、以前のように疲れて暗い影を落とした顔と鉢合わせる。 ルーピンは少し怯えたような彼女の表情を和らげようと、笑顔をつくった。 「先週、セブルスから聞いたんだ。薬のことを。」 「あ、…そうだったんですか。…ちゃんと飲めました?初めて作ったものだから心配で。 スネイプ先生がちゃんと見てくれたから大丈夫だと思うけど…」 「ああ、問題なかった。いつもより飲みやすかったしね。」 「…よかった。」 はほっとして自分の手元を見ていたが、 「ありがとう。」 その言葉に、は視線を上げて、また彼を見た。 薬を作ったのが知れてしまったのは本意ではなかったけれど、彼の気持ちに少しでも変化が起きてくれたら。 そんな淡い期待が彼女の中に浮かんだ。 でも、ルーピンの顔を見た途端、その期待はすぐに消えてしまった。 彼は、とても複雑そうな、苦しそうな表情をしていたから。 は今にも泣き出しそうなのに、無理に笑顔を浮かべて言った。 「…心配しないで下さい。私、もうこんなことしませんから。 今回は、その、自分の勉強の成果というか、最後まで薬を作り上げてみたかっただけなんです。 私が今後もあの薬を作るなんて、ルーピン先生に気を使わせちゃいますからね。」 自分のしたことが、逆に迷惑だったのだと彼女は思った。 一瞬、ルーピンは口を開きかけたが、から視線をはずすと、それ以上何も言わなかった。 それが肯定の印だった。 「それじゃあ」 彼に視線を合わすこともなく、は駆け足でその場を去った。 呼び止められることもないし、もう彼女が自分から振り返ることもなかった。 自室に戻り、はぺたりと床に座り込むと、なんだか自分が滑稽に思えてしまって。 悲しいはずなのに、目に涙を溜めながら笑ってしまう。 何か言って欲しかった。 私がやったことは無駄じゃなかったって、思いたかったのに。 あなたのそんな顔が見たくてやってきた訳ではないのに。 もう私が何をやっても、あなたを苦しませるだけだなんて。 何やってるんだろう、私。 「あーあ、終わっちゃった!」 最後の望みも、もう絶たれてしまった。 誰に聞こえるでもない、むなしい独り言が部屋に響くと、 梟のフィッチだけが、ホー、と可愛らしい声で答えてくれた。 (2007.8.1) なんだか展開遅すぎてごめんなさい。しかも一向に進展しない2人。 お気に召しましたら(*^-^*)→  web拍手 web拍手back / home / next |