|
あれから1週間ほどが過ぎた。 上手く避けているつもりでも、それにも限界が来るもので。 朝食の席に運悪くルーピンを見つけてしまって、は大広間へ入ろうかどうか躊躇した。 前は彼の姿を見ただけで、とても嬉しかったのに。今はまた悲しくなってしまいそうだ。 「おはよう」 「…、おはようございます」 ルーピンはが席に近づくと、少し笑顔を浮かべて声をかけてくれた。 も微笑もうとしたが、それは無理だった。 はわいわいと賑わう生徒たちの席を見ているが、 隣にいるルーピンのことで心がかき乱されていた。 結局、一言も交わすことはなかったけれど。 彼は今何を考えてるんだろう。 私に笑って声をかけられるぐらい、なんともないのかしら。 そう思うと、はなんだか悔しくなってしまった。 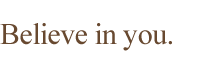 第30話 愛惜 彼から借りたもの、今すぐ全部返してしまおう。 さすがにもらったものまでは返せないけど。 私だって気持ちを切り替えようとしてるのよ、って伝えたかった。 …それが嘘でも、単なる強がりでも。 最後の授業が終わると、はルーピンの教室へ本や道具を抱えて訪れた。 扉が薄く開いていて、そっと中を伺う。 『ラッキー。』 誰もいないと思い中へ足を踏み入れた。 「…あ」 しかし、一番教卓に近い席で、机に突っ伏している誰かの背中があった。 彼はずっとそのままの体勢で、背中が微かに一定のリズムで上下していて、眠っているようだった。 『リーマス』 が近づいても起きる気配がなく、内心ほっとする。 腕の隙間から覗く顔が、とても疲れているようで。そういえばもうすぐ満月だった。 そっと横の机の上に荷物を降ろすと、はもう一度、ルーピンを見つめた。 こんなことしなければいいのに、と思いながら、教卓に置かれていた彼のくたくたのローブを その人の肩に、起こさないようにかけてあげた。 その時聞こえた、彼の寝息。 微かに感じた肩の温かさ。 ルーピンがこんなに近くにいて、触れられる距離にいて、は切なくなった。 触れてしまったら、またどんな拒絶をされるか分からない。 もうそれだけは耐えられなかった。 あなたを嫌いになれたら、憎めたのなら どんなに楽なのだろう でも、やっぱりだめ あなたが本当に好きなんだもの この想いを消したりなんてできない あなたが辛いのなら 一緒にいたいなんてもう言わないから だから せめてあなたのことを想っていてもいいですか? あなたのために、私ができることは何でもしたいの は愛しそうに彼の顔を見て、涙を溜めた目を細めると、そっとその部屋を後にした。 「…しまった。眠り過ぎた。」 ずっと同じ姿勢で痛みが残る腕を動かし、目をこするとルーピンは窓の外を見上げた。 先程まで夕焼けに染まっていた空は、もう真っ暗だった。 気だるい体を立ち上がらせようとした時、ふと、肩に自分のローブがかかっていたことに気付く。 視線をさ迷わせると、通路を挟んだ机の上に、本や魔法の道具が置かれていて。 ドキリとして入り口を振り返るが、誰もいない。 「……」 立ち上がり、彼女から返されたものをぼうっと眺めた。 それからしばらくして、 「ルーピン」 と呼ばれて振り向くと、スネイプがゴブレットを片手に、教室へ入ってきた。 彼の顔を見ると、ルーピンの顔が曇った。 知っていた。 が何事もなく、いつも通りスネイプの部屋へ行っていること。 「何だ、貴様も感傷にでも浸っていたのか?」 嘲るような視線に、ルーピンは耐え切れず睨み返した。 それを受けると、スネイプは口角を吊り上げて、呆れたように言った。 「こうなることは分かりきっていたはずだが…。 どれだけに酷い仕打ちをしたか、気付いていないようだ。」 分かってるつもりだった。それでもしょうがなかった。 ルーピンはぐっと拳を握ると視線を逸らし、投げやりに言った。 「君が慰めてやればいい」 その言葉に、今度はスネイプの顔色が変わった。 バシッ スネイプの杖の先から出た閃光が、ルーピンの胸を直撃し、吹き飛ばした。 そのままガタン、と大きな音を立てて、彼は教卓ごと倒れこんだ。 受身もまともにとっていなかったため、ルーピンは体の痛みに顔を歪ませる。 「…う、…スネイプ、」 「つくづく根が腐った奴だ。だから我輩は貴様が嫌いだ。」 睨み付けながら近付き、ルーピンを見下ろして、はき捨てるようにスネイプは言った。 その声は、いつもより一段と低い。 「飲め」 そう言ってスネイプはゴブレットをルーピンの口元に押し付けた。 無理やり強い力で、一気に薬を飲まされたものだから、ゲホゲホ、とルーピンは咽返る。 苦しかったが、不思議といつものあの苦さは口の中に広がらなかった。 全部飲み終わったのを確認すると、スネイプはゴブレットを彼から離した。 「毒でも入っていたらよかったがな。…この脱狼薬、誰が煎じたと思う?」 「…何?」 静かな口調で話すスネイプを、肩で息をしながらルーピンは見上げた。 「だ。」 ルーピンは驚きで目を見開いた。 「…まさか」 (薬は…病気の人たちに少しでも役立ててほしいと思って) うつむいてそう言った姿や、 疲労がたまって倒れ、気を失っているの顔を思い出す。 「数ヶ月も費やした結果がこの様だ。哀れなものだな。」 スネイプは呆然として見上げてくるルーピンを一瞥し、その場を去った。 あれは全て、私のためにしていたなんて。 「」 いっそのこと、彼のように憎んでくれたらいいのに。 嫌いになってくれればいいのに。 許さないでくれたらいいのに。 一方的に突き放した。 それなのに、どうして君はこんなことができるんだろう。 自分のしたことは後悔していない。 それなのに、のことを想うと、苦しさでどうにかしてしまいそうだ。 私は、君が思っているほど強くないんだ。 ルーピンは顔を手で覆うと、その場からしばらく動けなかった。 先程飲んだ薬の味が、口の中に広がって消えなかった。 (2007.7.22) 暗いし重いよ…。 お気に召しましたら(*^-^*)→  web拍手 web拍手back / home / next |