|
天候もようやく落ち着き、月も変わっていた。 再度のブラック侵入後、城の警備や生徒に対する規則はいっそう厳しくなっていたが、 イースター休暇なのに宿題がどの教科もたくさん出され、生徒たちはそれどころじゃなかった。 「はぁー気持ちいい!」 久しぶりに、清清しい青空が広がる一日だった。 は窓という窓を開け放ち、外に向かって気持ち良さそうに伸びをした。 そんな彼女が可愛らしくて、ルーピンは思わず見惚れていた。 「あっ、ちょっと見てないでこの本ちゃんと返してきてください! もう返却期限が切れてるのに、教授は生徒のお手本なんですからね。」 「はいはい、先生」 そう答えて、ルーピンは嬉しそうに本を手にして部屋を出て行く。 放っておくと何週間も掃除をしないルーピンに変わって、 エプロンをつけたは彼の部屋と研究室の大掃除をしていた。 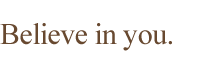 第27話 発覚 ルーピンが図書室へ行っている間、は部屋中を拭き掃除していた。 届かない場所は魔法で布を出して動かしながら。 「そういえば、いつもリーマスの部屋に来てばかりだから、たまには呼んであげないとね。」 そうしたら、何か手料理でも頑張ってつくってみようかな、なんて考えて顔がにやける。 こんな顔見られたら、またルーピンにからかわれそうだけど。 デスク周りを拭いていると、ふいにガタンという音が下から聞こえた。 普段あまり近づかないから分からなかったが、デスクの下に古めかしい棚が置いてあった。 が気になって膝をついてその棚を覗き込むと、それに反応するように棚はガタガタと揺れだした。 「何?ペットかな?」 鍵がかかっているので、その棚は手では開きそうになかった。 一瞬、何か危ないものが入っているんじゃないかと考えたが、それならルーピンが言っておくだろうと思った。 好奇心のほうが勝ってしまい、はエプロンのポケットから杖を取り出し、錠をはずした。 ―その瞬間 扉が開く音と同時に、何か大きい影が目の前に広がって、 はそれとぶつかった勢いで後ろに倒れこんだ。 訳も分からず、慌てて上体を起き上がらせて棚のほうを見ると、棚は空っぽだ。 驚いてあたりを見回そうと視線を横に向けた時、は思わず声を失った。 「…っ、」 目の前に、 夢に見た、幼いときに見た、 父親を殺して目の前で息絶えた あの人狼の姿があったからだ。 恐怖で息が詰まる。 なんでそこにその姿があるのかも分からない。 それでも、恐れていたものが目の前に現れて、声もあげられない。助けも求められない。 逃げなくては、と直感が訴えているのに、凍りついて震える手足は動かなかった。 その人狼は、記憶の中にあった恐ろしく輝く眼をに向けたまま、歯をガチリと鳴らし、 一歩手前で彼女を見下ろしている。 にはどうすることもできなかった。 その鋭い爪が彼女に迫り、が目を咄嗟に瞑った時、 「リディクラス!」 と叫ぶ声と、また棚が勢いよく閉まる音が聞こえた。 カツンカツン、と誰かの足音がして、は恐る恐る瞼を開いた。 そこにはもう、あの人狼の姿はなかった。 何が起きたのか全く分からなかった。まだ体が、まるで呪文にかかったように硬直したままで、動けない。 視界にルーピンを捉えると、はやっとほっとして、息をついた。 溢れ出ていた涙が床にぽたりと落ち、座ったまま、震える腕をおさえた。 「…その棚の中にはまね妖怪がいたんだ」 彼の声はまったく抑揚がなかった。 が見上げると、ルーピンは愕然とした表情をしていた。 は自分が一体何をしでかしたのか、なぜ彼がそんな表情なのか、 頭が混乱していて、この時は理解できなかった。 ただ、とても怖くて、今でも震えていて、側に来て抱きしめて欲しかった。 「リーマス」 耐え切れずに掠れた声でがルーピンの名を呼ぶと、彼は一瞬の戸惑いを見せたが、 やがて近づいて、座ったまま動けない彼女を抱きしめた。 が落ち着くまでに、しばらくの時間を要した。 その間、お互い無言で、顔も見えずにただ鼓動の音を聞いているだけだった。 やがて彼女が動けるようになると、ルーピンは腕を離した。 「…ありがとうございます」 がルーピンの顔を見ると、避けるように彼は視線をまね妖怪の入った棚に向けた。 「まね妖怪は、その人が一番恐ろしいと思うものに姿を変えるんだ。」 「…!」 その言葉に、はぎくりとした。 そして、ようやく分かった。 「…今のは、…あれは、私だった」 「っ、違います!あれはあなたじゃない!」 の否定の言葉に、ルーピンは過剰に反応した。 「何が違うんだ? 今のは人狼で、紛れもなく君が一番恐れているのはあれに成り果てた私だ!」 「あなたじゃない!私は父を殺されて、その時に見たのが今の人なんです! リーマスはリーマスでしょ?同じじゃない」 困惑した、怒りを露にした瞳を初めて向けられて、は必死になって言った。 でもそれは何の効き目ももたなかった。 「君は分かってない。私が狼の姿になれば、今のように私ではなくなる。 君の父親を殺していたのだって、私かもしれなかったんだ。」 暗い声でルーピンはそう言った。瞳には、もう輝きが無かった。 「リーマス、」 「今日はもういい、ありがとう。続きは一人でやるから。」 の言葉をさえぎって、ルーピンは立ち上がった。 もう顔を見てくれなかった。手も貸してくれない。 「待って、話を」 「今日は聞けないんだ。しばらく一人で考える時間をくれないか」 後姿のままそう言い捨てると、彼は自室へと向かった。 は呆然として、去り際に開いているドアから、彼が一人で片付けている背中を見た。 どうしても、今声をかけて、この状況をどうにかしたくてしょうがなかった。 でもその術がない。どうしたらいいのか分からない。 彼女の視線に気付いているはずなのに、が出て行くまでルーピンは振り向いてくれない。 それぐらい強い拒絶を感じて、改めては自分の愚かさに気付いた。 彼が秘密を打ち明けてくれない、なんて言っていた。 それなのに私はこのことを隠していた。 そんな大きな問題になるとは思ってなかった。 リーマスはリーマスだ、と思っていたから。 でも、それは私は彼の辛さが分かっていなくて、見たくない彼の部分に目を瞑ってきただけで。 だから、リーマスがこんなにもショックを受けるなんて想像もつかなかった。 彼のことを分かっているつもりだったけれど、それは大きな間違いだった。 (2007.7.15) やってしまいました。 お気に召しましたら(*^-^*)→ *web拍手を送る back / home / next |