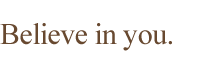 第24話 悪夢 それは、雷鳴が響くある夏の晩だった。 避暑に訪れていた別荘の一帯は、厚い雨雲に覆われていて、外は真っ暗だった。 雷の音が大きくて、怖くてなかなか眠れなかった。 2階の部屋でブランケットをかぶって、動く絵本を一生懸命集中して見ていた気がする。 突然、大きな雷鳴とともに部屋の蝋燭が消えて、真っ暗になって。 驚いた私は大きな声で母と父を泣きながら呼んだ。 それと同時に1階からとても大きな轟音と、母の私を呼ぶ声が聞こえた。 薄明かりの中で血相を変えて走りあがってきた母は、私を抱きしめると部屋の扉を閉め鍵をかけた。 ガタガタと震えうずくまる母の腕の中で、私は訳も分からずただ怯えた。 父は大丈夫だろうかと思っていると、私たちの部屋に何かが近づいてくる足音が聞こえて、 それに、多分父の足音も聞こえた。 父が何かを叫んで、大きな音が何度も聞こえて、ドアの隙間から明かりが漏れた。 やがて、耳を塞ぎたくなるような、人の断末魔の悲鳴が聞こえて、私はその得体の知れない恐ろしさに竦み上がった。 バリバリ、と部屋のドアが破られ、何かが部屋に入ってきた。 ベッドの陰に隠れていた母は、私を力強く抱きしめて、私の口をふさいだ。 父ではない何かの影は、私たちのすぐ横まで伸びてきて、 そして、私は見てしまった。 大きな、その獣の姿を。 それが私たちの姿を捉えると同時に、部屋の入り口から父の最期の声が聞こえて、目の前が真っ白になって。 その獣はものすごい悲鳴をあげて、崩れ落ちた。 一瞬何が起きたのか私は分からず、眩しさがおさまり目を開けると、横たわった獣は人の姿へと変わるところだった。 私たちの目の前で、その人は息絶えた。 そして同時に、私は父を失った。 声にならない声をあげて、ベッドから跳ね起きた。 は息を整えようと、呼吸を繰り返す。真冬だというのに、冷や汗が額や背に伝う。 「もう、やだ…」 顔を手で覆うと、ベッドの上で丸まった。 2月の雪が、暗闇の中を舞っていた。 ルーピンはノックの音に目が覚めて、眠気眼のままドアへと向かった。 パチパチと、暖炉の薪が燃え上がる音と、外の風の音だけが部屋に響いていた。 「?」 「ごめんなさい、こんな夜分遅くに…」 ドアを開けると、少し疲れた表情のが、寝間着の肩に薄い上着をかけて佇んでいた。 もうとっくに時計の針は深夜を回っていて。いつもと違う彼女の様子に眉を寄せるルーピン。 今にも消えてしまいそうな儚い彼女の肩を抱き、とりあえず部屋に入れると、はほっとため息をついた。 「大丈夫かい?顔色が悪いけど…何か飲む?」 「大丈夫です、何でもないんです。」 顔を覗き込むようにして心配してくれるルーピンに、は少し遠慮がちに言った。 「あの、隣で寝させてもらえませんか?嫌な夢を見て…」 いつもならまた子供扱いしているところだが、ルーピンは優しく微笑んで頷いた。 雷の日以外は、滅多にあの時の夢を見ることはなかったのに。 なぜ最近になってよくあの夢を見てしまうのだろう。 ずっと思い出さなかったのに。自分の中では、その記憶に目を向けるのも嫌だった。 閉じ込めていたかった。 あの夢を見るたび、あの時目の前で倒れた人を、リーマスと重ねてしまいそうになって そんな自分が本当に嫌だった。その度に首をふって、自分に言い聞かせた。 あの人はリーマスじゃない。 リーマスじゃない。 またが体を震わせると、なだめるようにルーピンは彼女の背中をさすってあげた。 その優しさと温もりが、次第に冷えたの体に伝わってくる。 は自分の表情を隠すように、横になっている彼の胸に顔をうずめて、その背を抱きしめた。 「ずっと側にいるから、ゆっくりおやすみ」 優しい声音でそう囁かれて、はそっと安堵の涙を流した。 あなたが好き。 この気持ちは偽りなんかじゃない。 あなたのためだったら、きっと私は強くなれる。 自分の弱さのために、失いたくない。 やっと見つけた大切な人だから。 あなたの全てを受け入れられるぐらい強くなるから。 だから もうあんな夢を私に見せないで。 (2007.6.25) はっ、こうしてまたすぐに問題が… お気に召しましたら(*^-^*)→ *web拍手を送る back / home / next |