|
思えば、楽しいクリスマスの記憶は数少ない。 大切な友を失った12年前から、私たちの時は止まったままで 幸せな思い出ももう増えることはなかった。 でも、この日は違った。 隣で静かに寝息をたてる彼女は、一晩中私の手を握ってくれていた。 目を覚ましたとき、とても穏やかな気持ちだった。 心の落ち着ける場所。 幸せなひととき。 それは、全ての腕の中にあった。 (話してくれて、ありがとう) 礼を言うのは私のほうだ。 その言葉に、その笑顔に、私がどれだけ救われたか。 君を好きになってよかった。 (本当の正体を目の前にした後も同じ気持ちでいられると思うか?) 大丈夫さ、セブルス。 彼女に醜い姿を見せなければいい。 彼女を傷つけなければいい。 あの姿まで愛してくれなんて言わない。 もうこれ以上は、何も望まないから。 だからこの場所を、 このひとときを どうか 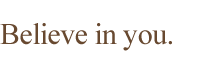 第22話 幸せな一日 はあ、温かい。心地いい。 なんだかとっても、幸せな気分… 「……」 ふっとまぶたを上げると、見慣れぬ天井が目に入った。 まだ眠い目をこすりながらぽーっとしていると、隣で笑い声が聞こえたので、目線を移す。 ルーピン先生が微笑んで私を見つめていた。 「…あ、…おはようございます」 「おはよう」 その優しい眼差しに見つめられて、この上なく幸せだとは感じた。 片肘をついての寝顔を見守っていたルーピンは、空いてるもう片方の手で、彼女の柔らかな髪を梳いた。 そのままその温かい手は、の頬を撫ぜる。彼の大きくて温かい手が、は大好きだった。 いちど瞼を閉じて、その気持ちよさを感じてから、は彼を愛しそうに見つめて言った。 「しあわせ」 本当に、なんで彼女はこんなに素直に言葉にしてくれるんだろう。 ルーピンは、目の前で眩しい笑顔を向けるが、可愛くてたまらない。 たまに初々しい反応を示すくせに。彼女は大人の女性だったり、少女だったりする。 「私もだよ」 そう言って甘い唇を塞ぐと、は鼻にかかったような声で微かに笑った。 顔を離し、不思議そうな表情で彼女を見下ろすルーピン。 「どうかした?」 「いいえ。慣れたかなぁ、と思ってたけど、たまにくすぐったいんです。」 はルーピンの鼻の下の髭に指先でそっと触れると、クスクスと面白そうに笑う。 「え?ああ、そうか…全然気がつかなかったよ。」 ルーピンも自分の髭に手をやって、きょとんとした。 剃ろうかな、なんてぽつりと呟くと、ダメです、と。 「私、あなたのその髭が好きなんですから」 ああっ、可愛いくて仕様がない 「メリー・クリスマス、先生、みなさん」 「メリー・クリスマス!!」 にこにこっと微笑みながらが大広間へ足を踏み入れると、ダンブルドアがはしゃいで席を用意してくれた。 スネイプが一瞬顔をしかめたし、あまり話したことのないトレローニーがギョロッとした目を彼女に向ける。 ハリーとロンは顔を赤くして、ちょっと疲れた表情だったハーマイオニーは嬉しそうに笑顔で彼女を迎えた。 クリスマスの食事がテーブルの上にずらりと並べられ、パーティーが始まったところだった。 スネイプとトレローニーの向かいの席、ハリーの隣に座ったは、昨日とはまた違うベージュの可愛らしいワンピースを着ていた。 「メリー・クリスマス、ハリー。楽しんでる?」 「はい、先生」 ふんわり笑うに、ハリーははにかんで答えた。蔑んだ視線を自分に送るスネイプなんて気にもしないで。 今日の彼女は、なんだかいつにも増して輝いているというか、…クリスマスだからだろうとハリーは思った。 「あ、あああ、あなた…!!」 持っていたスプーンをスープ皿にばしゃんと落として、トレローニーは口に手をあててを凝視した。 「な、なんですか?」 普通じゃない彼女の様子を見て、も少し驚く。 「今日はとても不吉なオーラに囲まれていますわよ。何かありまして?よろしければわたくしが占って…」 「え?!」 「そうかのう?」 驚いて眉を寄せるに代わって、ダンブルドアが朗らかに言った。 「わしにはいつもよりずっと、が内から輝いて見えるがのう。 きっと誰かから素晴らしいクリスマス・プレゼントでももらったのじゃろう。違うかな、?」 「はっ、…ええ、まあ…」 いつものように眼鏡の奥から温かい眼差しを向けられただけなのに、 はつい昨晩のことを思い出してしまい、頬が火照るのを感じた。 ルーピンがこの場にいなくてよかった、と何だか思ってしまった。きっと気まずくてしょうがない。 数人が目を丸くしてを見ている時、ゴホン、とマクゴナガルが咳払いをした。 「あら?そういえばルーピン先生はどうなさいましたの?」 マクゴナガルの冷たい視線を無視して、トレローニーはテーブルを見回して言った。 「先生はまた体調が優れないようです。」 ほんとは(今日はだるいから遠慮しておくよ)と言っていたことなんて、口が裂けてもは言えなかった。 「気の毒に。クリスマスにこんなことが起こるとは不幸なことじゃ。」 「まあ!わたくしの見るところ、ルーピン先生はお気の毒に、もう長いことはありません。 あの方自身も先が短いとお気づきのようです。 わたくしが水晶玉で占って差し上げると申しましたら、まるで逃げるように…」 「そうでしょうとも」 トレローニーの言葉をさえぎって、マクゴナガルがすぱっと言った。さすがにもその予言には閉口する。 「いや、まさか。ルーピン先生はそこまで危険な状態ではあるまい。 セブルス、ルーピン先生にまたいつもの薬を煎じてくれたのじゃろう?」 「はい、校長」 返事をしたスネイプをが見ると、彼はじろり、と彼女に冷ややかな視線を送った。 『私何か悪いことした?』 自室のドアを開けながら、先程のスネイプのことを思い出し、は首を傾げた。 クリスマスツリーの前を横切ろうとした時、はツリーの下で何かが動く気配を感じた。 「っ!!!わ、何??!!」 思いっきり身を引いて、落ち着いて見ると、そこには鳥かごが置いてあった。 「わぁ、…ふくろうだわ…!」 少し小柄で、綺麗な顔立ちのふくろうが、きょろきょろと目線をに運んでいた。 ほんのり淡いピンク色の羽がとても珍しくて、とても綺麗だった。 「…なんで?」 恐る恐る屈んで近づいてみると、鳥かごの上に赤いリボンでとめられたカードが目に入る。 " メリー・クリスマス この子はとても利口なふくろうだから、きっと君も気に入ると思う。 が私に幸せを運んできてくれたように、この子が君に幸せを運んでくれますように。 リーマス・J・ルーピン ” 「ルーピン先生…!」 彼が綴った文字から溢れてくる優しさが、とても愛しくて。 は胸にそのカードを抱きながら、潤んだ瞳でそのふくろうを見つめた。 「あたたかいな」 さすがによく見ている、とルーピンは感心せずにはいられなかった。 が昼に部屋から出て行った後気づいた、ツリーの下に置かれた彼女からのプレゼント。 "またぜひ一緒にお茶をしてください"というメッセージ付きの、品の良い模様が描かれたティーセット。 それから、"風邪ひいて倒れないで下さいね"と、彼女らしい一言が添えられたマフラーと手袋。 確かにこの前ホグズミードへ行った時、していなかったから。 つい嬉しくて外にいるわけでもないのに、手袋をはめてみてしまう自分が、なんだか滑稽で。 同じ色の落ち着いたグリーンのマフラーを自分の頬に寄せて、その感触を気持ちよく思う。 どうやら手編みのようで、微かにの香がした。こんなことしてるなんて、とても重症だ。 カツンカツン。 ふいに窓ガラスが鳴らされて、ルーピンは少し驚いて窓へと近づいた。 「ああ、君か。」 ガタン、と窓を開けると、冷たい冬の夜の風が部屋に吹き込む。 淡いピンク色のふくろうが、つい、と嘴に加えていたカードをルーピンの前に差し出した。 よく見ると、足元にはなにやらバスケットをぶらさげている。 ルーピンがカードを受け取ると、すぐにそのふくろうは飛び立ってしまった。 やっぱり。君は優しい人なんだね。 あの寂れた屋敷へと飛んでいくふくろうをしばらく見送って、ルーピンはため息をついた。 カードを開くと、また愛らしいの文字が。こんなにカードをもらうとなんだか得した気分になった。 " リーマス 素敵なふくろうをどうもありがとう。フィッチと名づけました。 あなたは何でもお見通しみたいで少し悔しいけれど。大切にしますね。 あなたのことが大好きです。 ・ " ルーピンは、思わず顔が綻ぶのをとめられなかった。 今夜は離れているはずなのに、 相手を想う気持ちは高まるばかりで。 心はずっと側にいるような気がして。 胸を焦がす熱い想いが、甘い吐息となって部屋に響いた。 (2007.6.13) ちょっといつもより長く。あ、甘すぎ… お気に召しましたら(*^-^*)→ *web拍手を送る back / home / next |