|
ホグワーツもとうとう休暇に入り、生徒たちのほとんどが帰省して城はがらんとしていた。 後に残されたのは数名の生徒と、教職員だけだ。 それでも、廊下にはクリスマスのリボンが飾り付けられてあったり、 鎧や彫刻は光を放ってクリスマスを祝っていた。 明日には盛大な飾りが施された大広間でクリスマスのランチがある。楽しみで仕方がなかった。 子供たちと何かして遊ぼうかしら、とは渡り廊下から見渡す景色を見て考えていた。 思えば自分も、休暇の時にはいつもホグワーツにいたから、残された生徒の寂しさが分かる。 肌寒いけれど、穏やかな天気のイヴだった。 星がキラキラと輝いて彼女を見送っていた。 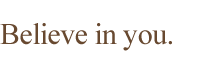 第20話 クリスマス・イヴ 「「メリー・クリスマス!」」 シャンパンの入ったグラスで乾杯すると、2人は美味しそうにそのグラスに口をつけた。 のおかげで、いつも散らかっていたルーピンの部屋もクリスマスの雰囲気になっていた。 ドアにはリースがかけられているし、そこそこの大きさのツリーもある。 いつもの明かりが消され、部屋はろうそくの明かりで温かな色に。 蓄音機からは落ち着いたクラッシックの曲が控えめに流れていた。 「わあ、おいしそう!ルーピン先生知ってますか? ホグワーツのレシピって、ほとんどがハッフルパフのものなんですよ。」 目の前のテーブルにある豪華なごちそうを皿にとりわけながら、は自慢げに言った。 「へぇ、知らなかったな。も料理が得意なの?」 皿を受け取ったルーピンの質問に、彼女はばつが悪そうに肩をすくめた。 「うーん、まあまあかな。得意じゃないんだけど…」 そんなの反応を見て、ルーピンは微笑んだ。 「ところでいつまでローブを着てるんだい?まだ寒いかな。」 「あっ、いいえ、そんなことないです。」 ルーピンに指摘されて、ますますは自分の顔が熱くなるのを感じた。 ローブを脱ぐのにここまで勇気がいることはない。は少し迷った後、自分の黒いローブを脱いで脇に置いた。 落ち着いた臙脂色で花柄のワンピースを着たは、なんとなく気まずくて視線を落とした。 じっと彼に見られているような気がして、何て言われるのか、それがとても気になるし恥ずかしいし。 彼女の明るくてウェーブのかかった髪や、白い肌が映える色のワンピースで。すらりとした手足が眩しいくらいだった。 「綺麗だよ、」 顔を上げると、ルーピンが照れたように微笑んでいた。 一番望んでいた言葉をもらえて、も嬉しくてはにかんだ。 「その、前にも言いましたけど、クリスマスは大好きなイベントだから気合が入っちゃうというか…」 「うん」 この日の温かい彼の微笑みと心地のよい雰囲気で、はとても幸せな気分になれた。 彼の表情から、きっとルーピンも同じように感じてくれていると思っていた。 2人でようやく学期が終わったことの労をねぎらったり、これまであった生徒たちのことを話したり、懐かしい話をしたり。 楽しい時間はあっという間に過ぎるもので、もう夜も更けていた。 紅茶とクリスマスケーキを食べ終えてしばらくして、ルーピンは時計を見ながら言った。 「もうこんな時間だ。そろそろお開きにしようか。」 「はい。」 いつも通りティーセットを片付けるルーピンを見ながら、はなんだか無性に寂しくなってしまった。 普段と一緒なのに。なんてことはないのに。まだ少し酔いが覚めてないのかもしれない。 「、大丈夫?立てるかい?」 無表情に机の上を眺めているの顔を、心配そうに覗くルーピン。 「ええ、はい。」 少しこわばった表情を浮かべながら、はローブを手にして立ち上がった。 どうしよう。 ルーピン先生の顔が見れない。 心のうちでは、特別な日だからと期待していたんだ。 帰りたくないなんて、思ってしまっている。 彼を困らせるかもしれないのに。 でも、今はただただ側にいたくて、離れたくなくて。 このままここにいたい。 このまま時が止まって欲しい。 私を引き止めてくれたらいいのに。 どうか追い出さないで。 もっと私を必要として。 お願い。 ばさ、とローブが床に落ちる音が響いた。 「?」 はルーピンにしがみついていた。 表情は見えないが、少し震えているを心配そうに見下ろすルーピン。 すがるような気持ちだった。今離れたら、幸せな時間が消えてしまう。 「帰りたくない」 まるで子供のようだと、は思った。それでも言ってしまった。 消え入りそうな声でそう呟いた後、は自分の言ったことが恐ろしくなって後悔した。 彼にもし突き放されたら、私はどうしたらいいんだろう。 ルーピンは動けず、何も言うことができずにいた。 少しの間が、にとってはとても長い時間だった。 お互いの温かさを感じ、心臓の音だけが鳴り響いていて。 「、」 肩に置かれたルーピンの手は、にとってひどく熱く感じられた。 彼は抱きしめる訳でもなく、の体を自分から離し距離を置いた。 それだけで、には分かってしまった。もう恐ろしくて、彼の顔が見れない。 それ以上、言わないで― 「泊めてあげるわけにはいかないんだ。すまない。」 このときの私は、自分の気持ちしか考えられなくて、わがままだった。 彼が何を考えているのか、私をどんなに大切に思っていてくれているのか、 どんな表情をして私を引き離したかなんて、 考えられないし、見ることもできなかった。 「…ごめんなさい…私、」 ただ突き放された腕が、全てのような気がして。 彼の笑顔の中に感じていた、拒絶のような気がして。 それだけで、悲しくて、涙があふれてきてしまった。 なんで、私はこんなに弱い人間なの。 だから、あなたも 私を信じてくれないの? は涙を隠すように、急いで床に落ちたローブを拾うと、何も言わずに走ってルーピンの部屋から駆け出した。 廊下を走り出すと、彼の自分を呼ぶ声が背中から聞こえてきたが、振り返ることはできなかった。 景色の良い渡り廊下のところで、は息をついてしゃがみこんだ。 失恋したわけでもないのに、なぜか悲しくて涙がとまらなくて、どうしようもできなかった。 ばかなことをしてしまった。 何をやっているんだろう。 幸せな時間を、自分から壊してしまった。 彼が愛しいのに、もっと近づきたいのに、わがままなんて言いたくなかったのに。 最悪だ。誘って断られて逃げ出したんだ。 プライドもなにもない。 もうルーピン先生の気持ちが分からない。 好きな素振りを見せながら、どこかで私との距離を置いている。 私は一体、どうしたらいいの? どうしたら、あなたの心に触れられるの? 私には、無理なの? 胸が苦しくてたまらない。 恋なんて、やっぱりしないほうがよかった。 (2007.6.2) ひとりで玉砕…。 お気に召しましたら(*^-^*)→ *web拍手を送る back / home / next |