|
学期が終わった週末、生徒たちは開放感でいっぱいではしゃいでいた。 もう休暇に入るので、最後とばかりに上級生はホグズミードでたくさんの買い物をしたり、 友達とお喋りをしたり、どんな休暇を過ごすかで頭の中がいっぱいだ。 その日は、雪が降り積もり、辺り一面銀世界だった。 寒い中、みんな帽子やマフラーで着込み、賑やかにホグズミードへ出かけていく。 「ハリー、どうしたの?あなたは行かないの?」 ロンとハーマイオニーに別れを告げて、大広間近くの廊下を歩いている時だった。 生徒たちと同じように温かい服装をしたが、ハリーの前方から声をかけた。 「はい、許可証がないので行けないんです。」 「そうなの、それは残念ね。あ、私あなたの保護者の方に手紙書きましょうか? せっかく3年生になってチャンスがあるのに…」 「いいえ、いいんです!ありがとうございます。」 にこやかに微笑むを前に、ハリーは頬を赤くして首を振った。 「…そうなの。じゃあ何かお土産買ってきますね。楽しみにしてて!」 ハリーの肩をとんとん、と軽く叩くと、は玄関へと向かった。 ちょっとした寂しさを抱えながら、ハリーも談話室へ戻った。 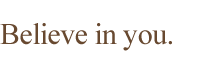 第18話 黒い犬 「はぁ、素敵!」 白い息を吐きながら、は目を輝かせた。 まるで物語の中に出てくるような、懐かしいホグズミードの冬景色。 家々はクリスマスムード一色で、屋根に積もった雪、飾られたイルミネーションがキラキラしている。 クリスマス好きのにはたまらない。 「それにしても寒いですね。風邪ひいてしまいそう!」 「そうだね、どこかの店に入ろうか。」 ルーピンとは、2人でホグズミードの街中を歩いていた。 が倒れた翌日は少し気まずかったものの、すぐにいつも通りの2人に戻ることができた。 それに、ルーピンに脱狼薬のことがばれていなかったことに、はほっとしていた。 2人で一緒にいられることに幸せを感じられた。お互い、一緒にいる今は余計なことを考えないで済む。 ふと、が立ち止まって、あちこちに同じようにある張り紙を見つめた。 「まだこの辺りにいるのかしら…」 の視線の先の、シリウス・ブラックの張り紙を見て、ルーピンは顔をしかめた。 「先生、スネイプ先生と同期だったんですね。この人もそうだと聞きましたけど、ご存知でした?」 「…ああ、同じ寮だったから。…友人だと思っていた。」 ルーピンが一瞬ためらったのを気にする様子もなく、はぽつりと呟いた。 「なんだか、悲しいですね。友達なのに…」 だんだんと吹雪いてきて、外を歩く人が少なくなってきたのとは反対に、ハニーデュークス店内は人でごった返していた。 並べられている懐かしいお菓子を手にして、も楽しい気分になる。 ピンクのココナッツ・キャンディーの袋を手にして、彼女が嬉しそうに横を見上げると、 「あらら」 隣にいるはずのルーピンは、店の奥のほうで女生徒たちにつかまっていた。 『男の先生は大変ね。』 肩をすくめてまた棚に視線を戻すと、背中のほうで「ハリー!!」という誰かの声が聞こえた。 『ハリー?』 気になって振り返って声のしたほうを見たが、人の頭でよく見えない。 『ハリーが来れる訳ないわよね…』 しばらくが視線を彷徨わせていると、ドアが開いて誰かが店から出て行った。 赤毛のロンと、ハーマイオニーが見えたような気がして、は眉を寄せる。 「ルーピン先生、ちょっとここで待っていてください!」 ざわめきの中での声に気付いたルーピンは、驚いて顔をあげた。 はそれを確認する暇もなく、出口へと向かった。 外に出ると、ますます風と雪が強まって、寒くて視界が悪かった。 辺りを見回したが、すでにロンたちの姿は消えてしまっていた。 『気のせいだった?』 吹雪く景色の中が目を細めると、ふと、視線の先に真っ黒いものを捉えた。 白い世界の中に、ぽつんと道の先で佇んで彼女を見つめている。 「あの犬…!」 は一瞬、ルーピンのいる店を振り返ったが、その犬が走り出してしまったので後を追うことにした。 『"叫びの屋敷"?』 雪の中走ってきたものだから、息もきれぎれには目の前の建物を見上げた。 呼吸をすると、肺の中に冷たい空気が入ってきて苦しかった。まさかこんなところに来るとは思わなかった。 が在学中もホグズミードの名所になっていた建物だ。 誰も住んでいないのに、夜になると叫び声が聞こえるといって誰も近寄らない場所。現にも近づいたことはなかった。 玄関の扉を恐る恐る開けると、廃れた薄暗いホールが目に入る。 外の吹雪のせいで、ぎしぎしと家が呻いているようで。 そこから続く部屋へ行くと、床や壁にはそこらじゅうに染みやキズがあったり、穴が開いていたり。 家具もあるがどれも壊されていてボロボロだった。ひんやりとした部屋の空気に、はぞくりとした。 その大きな黒い犬は、火のない暖炉の前でブルブルと体の雪を振り落としていた。 はそれを見て、少しほっとした。幽霊がいると聞いていた場所だが、今目の前にいるのは命のある犬だ。 彼女が近づいても、その犬は警戒することもなく、力なさげにその場に座ってを見上げた。 「あなた、ここに住んでいるの?」 が聞くと、犬はワン、と弱々しげに答えた。 「まあ、賢いのね。私の言っていること分かるみたい。」 よく見ると、その犬はやせ細っていて、今にも息絶えてしまいそうだった。 が杖を取り出し、暖炉に炎を灯すと、部屋の中は温かい色に変わった。 「こんなものしか今はないんだけど、」 と言いながら、彼女は黒い犬の目の前に、水の入った皿とアップルケーキが載った皿を出した。 ケーキをちぎってやると、犬はワン、とお礼を言って食べ始めた。 「こんなところに一人でいて、寂しかったでしょう。」 はその犬の横に腰掛けて聞いてみたが、食べるのに夢中で返事はないようだ。 荒れた薄暗い部屋の中、まるで外界と隔てられたような場所で、ただ一人ぼっち。 きっと孤独でたまらない。 私はきっと耐えられない。 そしてふと思い浮かんだ、大好きな人の顔。 彼もまた満月の夜に、ただ一人だけで、その孤独に耐えてきたんじゃないだろうか。 寂しくて、悲しくて、苦しかったんじゃないだろうか。 今見ている景色が、彼が見ていた景色と重なっているような気がして、 は言い知れない寂しさで胸がいっぱいになる。 最近、自分でもどうかしてると思うけれど、また涙がこみあげてくる。 「…やっぱり、あの人の側にいたい。」 (2007.6.1) 中途半端に他のキャラを絡ませてしまいます(汗。 お気に召しましたら(*^-^*)→ *web拍手を送る back / home / next |