|
次の朝からは上機嫌だった。 どれだけ大変かは分からないけれど、とにかく脱狼薬を作れるようになれるかもしれない。 そんな希望が持てたからだ。 彼を信じて待とう。 嘆いたり、悩んだりするよりも、今私ができることをすればいいんだ。 元気そうなが、ルーピンと楽しそうに話している姿を、 朝食の席から見ていたハーマイオニーは、ほっと安心したようなため息をついた。 「どうしたんだ?ハーマイオニー」 「あ、ううん。なんでもないわ。」 そう言ってハリーに曖昧に微笑むハーマイオニー。 ハリーはハリーで、最近ルーピンと年明けに個別指導をしてもらう約束をして、わくわくしていた。 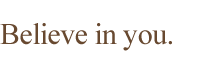 第14話 冷たい微笑み 「あ、ごめんなさい。私そろそろ行かなくちゃ。」 コト、とカップを置いて、脇にあったローブを手にする。 夕食後、ルーピンの部屋でいつものようにお茶をしていただったが、 今日は30分も経たないうちにその場を去ろうとする。 さすがにルーピンも少し驚いた顔をして、立ち上がる彼女を見上げた。 「約束かい?」 「ええ、そうなんです。ちょっと大事な用で」 すまなさそうに言っては出口のほうへ行くと、ルーピンも見送るためにドアまで歩いた。 「送ろうか?またこの前みたいなことがあっても」 「大丈夫ですよ。杖も戻ってきたし。」 ふふ、と嬉しそうに振り向いて笑うに、ルーピンは少し複雑そうな顔をする。 「君の防衛術は、あまり頼もしいものじゃないからね。」 現に何度かが倒れているところを見ているルーピンだけに、余計心配になった。 「じゃあ、あなたに今度教わることにします。」 「それがいいよ。」 そう言ってルーピンはの頬に軽くキスをした。 見上げたの瞳には、彼のまた切なそうな瞳が映し出されていた。 目の前のテーブルに積み重ねられた本の山を目にして、は絶句した。 「どうかしたか?」 いつもの声音に楽しそうなものが混じっているけれど、は答えられなかった。 なぜなら、目の前の書物は何十冊もあり、さらにどれも1巻がとても分厚かったからだ。 「お前に必要だと思うものを全部抜き出してやった。 これだけ読むには半年はかかるだろうな。」 「は、半年??!!」 『これって嫌がらせ?!』 とが思うほどの量だった。何かの罰則のようだ。 しかも、きっとどの書物も細かい文字がいっぱいだろう。 「まぁせいぜい頑張りたまえ。 お前が薬を完成させる頃には、ルーピンは既にホグワーツにいないかもしれんがな。」 そう言ってスネイプはにやりと笑った。 その言葉に腹が立ったけれど、は適当な1冊から、とりあえず読むことにした。 スネイプの事務室のソファで、メモをとりながらページをめくり続けた。 が本を読んでいる間、スネイプは自分のデスクで何やら仕事をしているようだった。 何時間かが過ぎて、集中力がきれたので、は以前から気にかけていたことをスネイプに話した。 「先生は、ルーピン先生のことあまりよく思っていないようですけれど 何かあるんですか?」 の質問に、スネイプは顔を上げずに答えた。 「答える必要もない。人狼を誰がよく思うと言うのかね? 我輩は奴が教師に任命された時、反対したにも関わらず、ダンブルドアが奴を起用した。 だからシリウス・ブラックが忍び込むと言う事態になったのだ。」 「…どういうこと?」 少し緊張した声が聞こえてきたので、スネイプはの顔を見て言った。 「ルーピンがブラックを城内に招き入れたのだ。」 「そんな!」 驚くを見ると、スネイプは口角を上げた。 信じられない、といった表情で、スネイプの話を聞く。 「偶然なことに、我輩は奴らと同学年だった。 ブラックとルーピンは何をするにも、それは仲のよい友人だった。 奴らの悪戯で危うく我輩も殺されそうにもなったことがある。」 「でもっ、人を危険な目にあわせるようなこと、ルーピン先生は絶対にしないと思います。 今はもう友人ではないかもしれないし、何か誤解があるのかも…」 「人狼が何を考えているかなど、我らに分かるものか。 、お前も気をつけたほうがいい。いつ危険な目に合うか分からんからな。」 は困惑した表情のまま、下を向いて黙ってしまった。 そんなこと、信じられるはずがない。 本を読んでいたらいつの間にか眠ってしまっていて、 けだるい体を起こすと、その部屋にスネイプはいなかった。 時計に目をやり、はっと立ち上がる。もう次の日の朝になっていた。 地下室なので、日差しが届かないから朝の感覚がない。もう朝食の時間だ。 「なんで起こしてくれなかったの!!」 慌てては自分の部屋へ走り出した。 朝食が終わる時間にはまだ余裕があるから、シャワーでも浴びて着替えないと。 たまにすれ違う生徒に挨拶しながら、自分の事務室への廊下を曲がると、 は思わず足を止めてしまった。 『しまった…暖炉を使えばよかった』 ルーピンが腕組みをして、の事務室近くの壁に寄りかかって立っていた。 が近づくと、その足音に気がついてルーピンは彼女のほうを見た。 一瞬垣間見えた厳しい視線を隠すように、彼は微笑んだ。 「おはよう、。もう朝食は済ませたのかな?」 「いいえ。ちょっと…朝の散歩をしてたので、お腹ペコペコです。」 なんだか気まずくて、はルーピンの視線を避けるようにしてなんとなくにこりと笑った。 スネイプの部屋で寝過ごしたなんて言ったら誤解を招くし、本を読んでいたといっても嘘臭い。 「そう。一緒に行こうかと思っていたが… やはり私は先に行ってようかな。君も顔ぐらいゆっくり洗いたいだろうしね。」 いつもより張り詰めた声音で、その言葉を聞いて、はその場に凍りついた。 嘘だというのはばれていた。言わなければよかった。 『ルーピン先生って…怖い』 顔では笑っているけれど、どこかぴりぴりとした空気を感じ取って、 はそれ以上言い訳も考えられなかった。 (2007.5.19) 男の嫉妬はみっともないけど好きですw お気に召しましたら(*^-^*)→ *web拍手を送る back / home / next |