|
クィディッチ戦で吸魂鬼が入り込んで、怪我をしたハリーも回復し、 やっと周囲も落ち着き始めた頃。 寒さがだんだんと厳しくなってきて、生徒たちもマフラーや手袋、耳あてをつけ始めた。 そんな姿を見れば、冬の訪れが間近なんだと実感できた。 先生方の中でも、気が早い人がいて、もう自分の教室にクリスマスの装飾をし始めていた。 まだ11月なのに。 もその一人だった。イベントが、特にクリスマスの雰囲気が大好きだったは、 はりきっていつも簡素な自分の教室を、修理から戻ってきた杖で飾り付けていた。 大きなツリーは必須で。壁という壁にリースやら雪だるまや靴下といったモチーフをペイントする。 キラキラ輝く、無数の魔法のボールを天井からぶら下げたときには、 さすがに生徒から「まぶしくて授業にならない」という苦情がでたので控えめにしておいた。 マクゴガナルから注意されたけれど、は聞き流すことにした。 その教室は、生徒たちを愉快にし、他の先生方を呆れさせた。 ただ一人の先生を除いては― 「はは、これはすごいね。どこかのパーティー会場みたいだ。」 そう言って笑うルーピンを見て、は満足げに微笑んだ。 「そうでしょ?これぐらいやらなきゃ、気分が盛り上がらないと思って! クリスマスが近くなったら、雪も降らせようと思うんです。ほらっ」 が杖の先を天井に向けてふると、見上げる二人の上に粉雪が降り始めた。 天井は星空に変わる。 「君は本当にクリスマスが好きなんだね。」 可笑しくてクックッと笑うルーピン。少し口をとがらせては、 「こんなロマンチックな場所で、キスでもしたら素敵じゃありませんか?」 と言い、少し挑発めいた視線を彼に送る。 ルーピンは眉を少し上げると、杖を持つ彼女の右手に自分の手を重ねて、 そのまま教室のドアを魔法で閉めた。 「子供っぽいとは思っていたが、最近は小悪魔みたいだね。」 「ルーピン先生、そうやっていつも、」 が抗議しようとすると、ルーピンが空いているほうの手で彼女の口に自分の人差し指をあてた。 「その“ルーピン先生”というのはもう止めてくれないか? なんだか生徒と付き合っているようで…」 「私ってそんなに子供っぽいのかしら?」 「、リーマスと」 拗ねているの言葉を無視して、ルーピンは愛しそうな優しい眼差しを彼女に向ける。 そんな彼の表情が、には安心できて。でもまだ自分が子供のように甘やかされているように思えて。 は少し頬を赤らめて、彼の瞳を見上げながら言った。 「…リーマス」 「よろしい」 ルーピンの満足げな表情を見て、やっぱり腑に落ちないといっただったが、 彼の唇が降りてきてしまえば、そんなことは考えられなくなってしまうのだった。 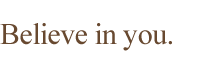 第13話 暗黙の取引 「スネイプ先生」 珍しくいつもの笑顔をせず、真剣な表情で話しかけられたものだから、つい自分の事務室に入れてしまった。 しかし、その後スネイプは後悔することになる。 「ルーピン先生の飲んでいる薬、煎じているのはスネイプ先生でしょう?」 「そうだ。それがどうかしたのか、?」 スネイプと向かい合うように立っていたは 意を決したように口を一度ぎゅっと結ぶと、思い切ってそれを口に出した。 「私に教えてください。その薬の作り方を」 一瞬驚いて固まったかと思うと、次の瞬間、スネイプは呆れたように、陰湿な笑いを顔に浮かべた。 まっすぐ彼を見つめているを見据えながら。 「なぜだ?そもそも何の薬か知っていて言っているのか?」 「はい、知っています。」 「ほう、知っているのか。意外だな。 ダンブルドアからはお前には言わないよう口止めされていたが」 『…ダンブルドアが?』 疑問が浮かんだの顔を無視して、スネイプは愉快そうに続ける。 「奴の口から直に聞いたとは思えん。ひたすら生徒にも隠しているからな。」 「スネイプ先生が生徒に出したレポートのせいで、私は気付いたんですよ。」 にはなぜだか分からないけど、スネイプは以前からルーピンを嫌っているようだった。 今のルーピンの秘密を話して、の表情を見たスネイプは、とても満足していた。 「それで?お前は善意で奴のために薬を煎じてやろうと思ったのか? それともあの化け物に骨抜きにでもされたか?」 「その言い方は止めてください!」 が少し口調を荒げると、スネイプはまた口元をゆがめて笑った。 「先生は仰いましたよね、私なら脱狼薬くらい作れるようになっていただろうって。 それなら、私はルーピン先生のために薬を作れるようになりたい。 スネイプ先生の仕事も軽減されるし、悪い話じゃないでしょ?」 「だめだ。あの薬は仕方なくダンブルドアから頼まれて煎じてやってはいるが、 ひとつ煎じ方を間違えれば命に関わるものだ。さすがに校内で人殺しはしたくは無い。 それにお前にかける時間などない。」 急に厳しい目を向けられて、はぐっと自分の拳を握った。 「私は間違えたりしないように、必要であればどんな知識でも身につける努力をします。 先生の手を煩わさないように、自分ができることは自分でします。最低限の助言しか頂かないようにします。 だから、どうかお願いします!」 まっすぐに、本当に真剣な、思いつめたの眼差しを受けて、スネイプも言葉につまった。 は昔から真面目で勤勉で、一度決めたら頑固なところが印象的な生徒だった。 魔法薬学だけ妙なセンスを発揮して、スネイプは感心していたものだ。 ここで断ることは簡単だったが、確かにが言っていたように仕事が減るというのは頷けた。 ひたり、とスネイプはに冷たい視線を落とした。 そして今、もうひとつ見つけたのだ。 学生時代から憎らしかった奴らの一人、ルーピンを、苦しませる方法を。 「我輩は教えたりしない。 だがお前が勝手にやるのなら話は別だ。我輩の手も煩わされることはない。」 言われた意味が、いまいち分からなくて、は微かに首を傾げた。 それをチラリと見やって、スネイプはくるりと彼女に背を向けて話し始める。 「この事務室には数え切れんほどの魔法薬に関する蔵書がある。 全部読めとは言わん。脱狼薬に必要なものは、それでも読んで理解するのに相当な時間がかかる。 薬の調合法だけ読むだけではすまないからな。 それを全部理解したうえで、自分で作ってみろ。必要な材料は自分で集めるんだ。 用具は教室にあるものを使えばいい。ただし、脱狼薬を調合する時は、我輩が立ち会う。」 「…あっ、ありがとうございます!」 話に聞き入って、しばらくぽーっとしてしまったが、は嬉しそうに礼を言った。 『それって、結局手助けしてくれるってことよね』 「蔵書は外に持ち出すことは禁止している。だからこの部屋で読むことだ。 我輩も忙しい身なのでね、ここに出入りするのは夕食後以降にしてもらおう。」 「あ、はい、分かりました。じゃあ、できるだけ毎晩ここへ来るようにします。私も本業があるし。 …ルーピン先生には薬のこと黙っていて頂けますか?」 「ああ、承知した。」 笑顔になって頭を下げたが退室するのを見送って、スネイプは面白そうにぼそっ、と呟いた。 「言うわけ無いではないか」 (2007.5.19) スネイプ先生は意地悪に書いてますけど、いい先生です。 お気に召しましたら(*^-^*)→ *web拍手を送る back / home / next |