|
「誰か、ダンブルドア先生を呼んで!急いで!」 監督生のパーシー・ウィーズリーの声が廊下に響いた。 がやがやと、生徒たちは無残な肖像画の姿に驚き、集まり、 そして階段下で横たわるを取り囲んでいた。 「先生!」 「だめだ!動かしちゃ。頭を打っているみたいだから。」 蒼白な顔のの側に寄って、泣きそうになる生徒たちもいた。 「さよう、みな落ち着くんじゃ。マダム・ポンフリーが今駆けつけておる。」 いつの間にかの横に立っていたダンブルドアが、 膝をついて彼女の息を確かめ、そう言った。 教職員も騒ぎに気付き、まさに駆けつけているところだった。 「!!」 意識のない彼女の姿を見つけ、ルーピンの顔は真っ青になった。 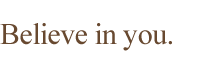 第10話 ボーダーライン アズカバンを脱獄したシリウス・ブラックが、ホグワーツ城内に侵入し 教師と肖像画を襲ったと言うので、城中が混乱した。 ダンブルドアの指示のもと、全校生徒は大広間へ集められ、その夜はそこで生徒たちは寝ることになった。 監督生が大広間を見張りながら、教職員は城をくまなく調べるよう言われた。 「リーマスよ」 先生方が大広間を出て行こうとしたとき、ルーピンはダンブルドアに呼び止められた。 「なんでしょうか?」 「の様子を見てきてくれんかのう。落ち着いた頃に話を聞きにいかねばならんが。 今は君が一番適役じゃろう。」 「はい、分かりました」 ルーピンを見送った後、ダンブルドアは静かなため息をついた。 ゆっくりとまぶたをあげると、見慣れぬ天井が視界にはいってきた。 「?ああ、よかった。気がついたのね。」 は呼ばれたほうに視線を移すと、校医のマダム・ポンフリーがほっとしたような表情をしていた。 ズキズキ頭や体のあちこちが痛くて、いまいち状況が飲み込めなかった。 「…私…?」 「階段から落ちたようで、体中を打って気を失っていたのよ。 幸いどこも骨折していなかったから、まだよかったけれど。」 少し頭をずらして周りを見回すと、そこは病室だった。夜も更けていて、薄暗い。 重い体を腕で支えて、上半身だけ起きようとしたが、体の節々が痛くて マダム・ポンフリーに支えられてやっとのことで体を起こした。 体中に湿布やら包帯やらが捲かれているようだった。 「しばらく安静にする必要がありますからね。無理をして起きたりしたら駄目ですよ。 今日はここで寝なさい。」 「…はい。ありがとうございます。」 何か欲しいものはあるか、と聞かれ、は力なく首を振り、弱弱しく微笑んだ。 ちょうどその時、ルーピンが医務室へ入ってきた。 「」 「ルーピン先生」 名前を呼ばれて、心配そうな顔をしたルーピンを見ると、はほっとして泣きそうになった。 二人の様子を見たマダム・ポンフリーは、さっと用具を持ち立ち上がった。 「私は事務室にいますから、何かあったらすぐ呼ぶんですよ。 ルーピン先生、あまりに無理はさせないように。」 最後のほうをきつく言うと、マダム・ポンフリーは扉を閉めて、医務室から出て行った。 ルーピンはのベッドの横の丸椅子に腰をかけると、の顔をじっと見た。 「落ち着いたかい?」 「はい。…ルーピン先生、私、シリウス・ブラックを見ました。」 少しためらった後、はまっすぐ彼の目を見て切り出した。 複雑そうな表情で、眉を寄せてを見つめ返すルーピン。 「君は、ブラックに?」 「いいえ、私が階段から落ちたのは自分のせいなんです。 彼は私に危害を加えるつもりはなくて、むしろ逃げようとして…、」 手でぎゅっとシーツを掴みながら、ゆっくり思い出すように話す。 「私、その時杖も持ち合わせてなかったから、階段を下りて逃げる彼の服を掴んだんです。 そしたら…突然彼の姿が目の前から消えて…、それで、気付いたらここに…」 「君は、なんでそんな危険なことをっ」 「だって、そのまま放っておける訳ないじゃないですか、城内には生徒がいるんですよ?」 少し怒っているような口調のルーピンに、も思わず強く言ってしまった。 彼は一度口を閉じると、ひとつ息を吐いた。 「すまない。 私は、君が宴会にすぐ来ると言ってたのに来なかったから、心配していたんだ。 でも騒ぎを聞いて、気を失っている君の姿を見て、本当に後悔したよ。 なんで君が来ないことを不審に思って、早く探しに行かなかったんだろうって。」 「いいえ、そんな…」 真剣で、それでいて気遣うようなルーピンの視線と言葉に、の胸は愛しさでいっぱいになる。 やっぱりあなたが好きだ。どうしようもなく惹かれている。 あなたに触れたい。あなたに愛されたい。 「大事に至らなくて、本当によかった。」 「…ルーピン先生」 本当は、今すぐにでも彼女に手を伸ばして抱きしめたかった。 それでも自分の意志を抑えつけて、ルーピンはに優しく微笑もうとした。 でも、彼女の一言が― 「心配してくれるのは、同僚として?」 「教師だから?」 驚くルーピンを、は思いつめたような瞳で見上げていた。 そんな彼女の瞳を見てしまって、どうしてそのまま微笑んでいられようか。 「違う」 と短く答え、ルーピンはを抱きしめた。 手を伸ばさずにはいられなかった。 いたわるように、そっと優しく、その腕で彼女の背を包む。 温かくて心地のいい彼の腕の中で、の瞳からは自然と、涙がこぼれた。 お互いの鼓動が、ひとつになっている気がした。 これ以上好きになってはいけないと思っていたのに もう抑えきれない想いが 一線を越えてしまった (2007.5.13) たどりついた。 *web拍手を送る back / home / next |