|
今までそんなに経験豊富っていう訳じゃないけれど、 人並みに恋愛をしたことはある。 でも今回の失恋は、これまでで最悪の、手痛いものだった。 もうしばらくは人を好きになるなんてできない! そう思って落ち込んでいた矢先、恩師からの1通の手紙で またしても私の運命は大きく変わることになった。 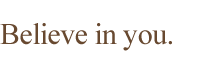 第1話 ホグワーツへ 10年以上も前、同じ汽車に乗って心躍らされた自分の姿を、今目の前を行きかう幼い生徒たちに重ね、思わず微笑む。 季節は夏の終わり、まだ少し暑さが残る。魔法使いと魔女の卵たちを乗せたホグワーツ特急は、ロンドンから郊外へと走り始めた。 久しぶりに友達と再会する生徒たちの笑い声が、コンパートメントから聞こえる。とても賑やかだった。 まだ少し緊張した面持ちの、可愛らしい生徒たちもいる。きっと1年生なのだろう。 『私も始めてホグワーツに行くときは、わくわくドキドキしてたわね。』 は空いている、適当なコンパートメントを見つけて自分の荷物を棚に上げた。 このひとつひとつの動作も、自分が学生の頃を思い出させてくれる。 学生の頃と自分は立場も年齢も変わってしまったけれど、今もわくわくしている気持ちは変わらない。 が外の景色を眺め物思いにふけっていると、2人の小さな女の子が同じコンパートメントに入ってきた。 「あ、あの、座ってもいいですか?」 頬を真っ赤にして遠慮気味に聞いてくる彼女たちに、は優しくにっこり微笑むと、どうぞ、と言った。 『かわいいなぁ』 は無類の子供好きだった。彼女たちの荷物も棚の上にのせる。 「あなたたち1年生?」 「はい!…あの、ディーンっていいます。こっちの子は友達のマリー。」 2人はにつられて、ほっとしたような顔をして笑った。 「私はっていうの。今学期から先生になるから、私も先生の1年生ってとこかしら。 よろしくね、ディーン、マリー。」 3人はのんびりと、おしゃべりをして時間をすごした。 が魔法で紅茶やおいしそうなお菓子を華麗に出す姿に、ディーンとマリーは喜んでいた。 「そういえば先生、私たち、さっきハリー・ポッターを見たのよ!」 「そうそう、噂どおり額に稲妻のかたちした傷があったわ!」 マリーが興奮気味に話すと、ディーンもきゃっきゃっと盛り上がる。 「ハリー・ポッターかぁ」 は今思い出した、とばかりにぽかんとつぶやいた。 噂でしか聞いたことのない、伝説的に今有名な"生き残った男の子"ハリー・ポッター。 一体どんな子なのだろう。 キキィーーーーーーーーーーーーーー!!!!!! 突然、ブレーキの音が列車全体に響き渡った。 思わずも生徒たちも体勢をくずし、棚の上の荷物もブレーキの反動で落ちてきた。 「大丈夫??!!」 はディーンとマリーを抱き起こす。そして次の瞬間、ぞくりとした悪寒が彼女の全身を駆け巡った。 はっとして顔を上げ、コンパートメントのドアを見上げる。 すると、今まで日が出ていた景色が、いつの間にか暗くなっていた。 夏なのに、底冷えするような冷気が、コンパートメントの外側から漂い始める。 「…せんせぇ…」 怯えた表情をしたディーンとマリーは、にいっそう強くしがみついた。 「…これは一体、何なの?!」 吐息が白い。 「…!!!」 ガラスの戸が冷気で白くにごる。そしてドアの向こう側の者の影を落とす。 大きい黒い影だ。 は視線をその影からそらさず、懐から自分の杖を取り出し身構えた。 彼女の杖の先は、ガタガタと震えていた。 カタン、とドアに細い、骸骨のような指先がかかり、ドアがゆっくり開けられる。 ドアの向こう側の黒い影の正体を見た瞬間、 の心は恐怖に押しつぶされた。 意識を手放す直前 の耳に聞こえたのは男の断末魔の悲鳴 そして脳裏に浮かんだのは ―獣の目 パンパン、と頬叩かれる。 「大丈夫かい?」 痛い。痛いわ。 もうちょっと優しい起こし方っていうものがあるんじゃない? とのんきな思考をめぐらす。 すっと目を開けると、近くで私を見下ろしているおじさんの顔が目に入る。 鳶色の髪も色あせたような、やつれて病人のような… なんだかくたびれた感じの人だ。それが第一印象。 「…ん…、あれ…」 身体を起こそうとするが、力が入らない。嫌な汗をかいたのか、まだ寒気もする。 「先生、大丈夫?!」 ディーンが心配そうな顔して、半ベソをかきながらを覗き込む。マリーも一緒だ。 「あ、よかった。無事だったのね。」 血の気のない顔なのに、はほっとして微笑んだ。 「君が無事じゃないみたいだけどね。」 を抱き支えてくれている紳士は、呆れたような顔をしている。 「す、すみません。力が入らなくて…」 そう言いかけると、彼はを支えて座席に座らせてくれた。 「ありがとうございます。一体、何があったんでしょうか?」 「吸魂鬼(ディメンター)だよ。脱獄した囚人を探してうろついている。 彼らが去った後、車掌と話しに行く途中、君がここで気を失っているのを見つけたんだ。」 は自分が情けないと思った。肝心のときに気を失って、生徒を傷つけることになっては手遅れだ。 「君が守った生徒も、他の生徒もみんな無事だよ。心配しないで。」 の心中を察したのか、彼は優しい口調でそう言って微笑んだ。 「はい…」 なんだか慰められているようで、もどかしい気持ちになってしまい、は困ったように笑った。 「さてと、じゃあ私は車掌のところへ行くよ。」 側にいたディーンとマリーの頭を優しくなでると、彼は立ち上がった。 「あ、私も一緒に…!」 「この子達も心細いだろうから、君は側にいてあげなさい。」 「え?!あ、…はい。ありがとうございます、ミスター…」 礼を言われた相手は、にっこり笑うと、 「ルーピンだ。リーマス・ルーピン。」 「ルーピン、先生ですよね?私は・」 彼の職業は聞かなくても分かる。に対してもまるで生徒に対するような口調だ。 「ああ、。そうだ、これを食べなさい。元気になるから。」 そう言ってぼろぼろの継はぎだらけのローブのポケットから出てきたのは、銀紙に包まれたチョコレートだった。 まさかそこでチョコが出てくると思わなかったは、あっけにとられ、思わず受け取ってしまった。 は驚いた顔をルーピンに向けると、彼は善良な笑顔を浮かべ、そのままコンパートメントを去った。 ドアが閉める音とともに、なんとも複雑な思いがの胸にこみあがってくる。 青かった顔を赤くして、彼女はつぶやいた。 「こ…子供じゃないんだから」 教師としての彼の優しさと冷静さを尊敬するとともに 自分の未熟さを思い知る。 そしてそんな自分をまるで生徒のように扱うルーピンが腹立たしかった。 これが彼女とリーマス・ルーピンの出会い。 彼女にとって尊敬できる人、そして― (2007.5.5) はじめてしまった… *web拍手を送る home / next |